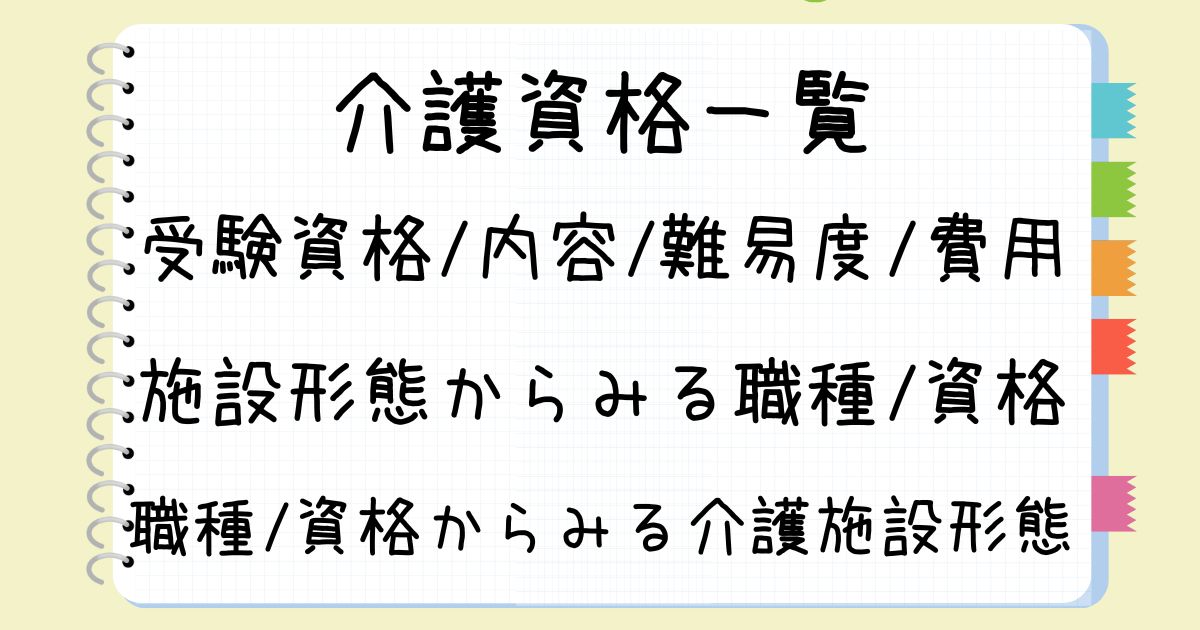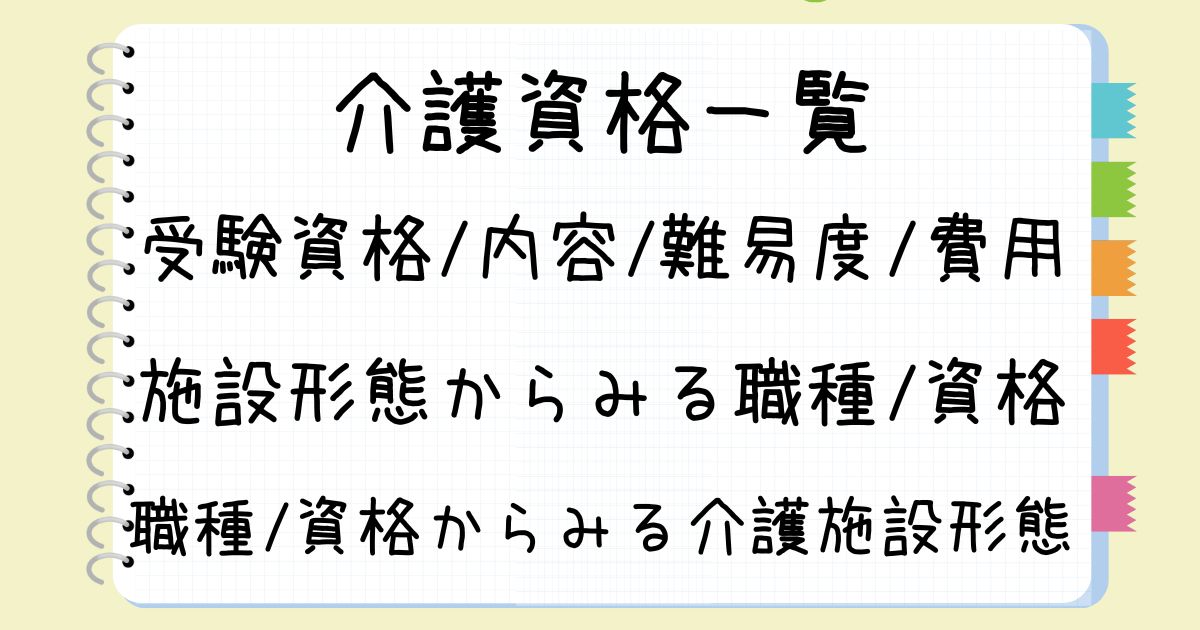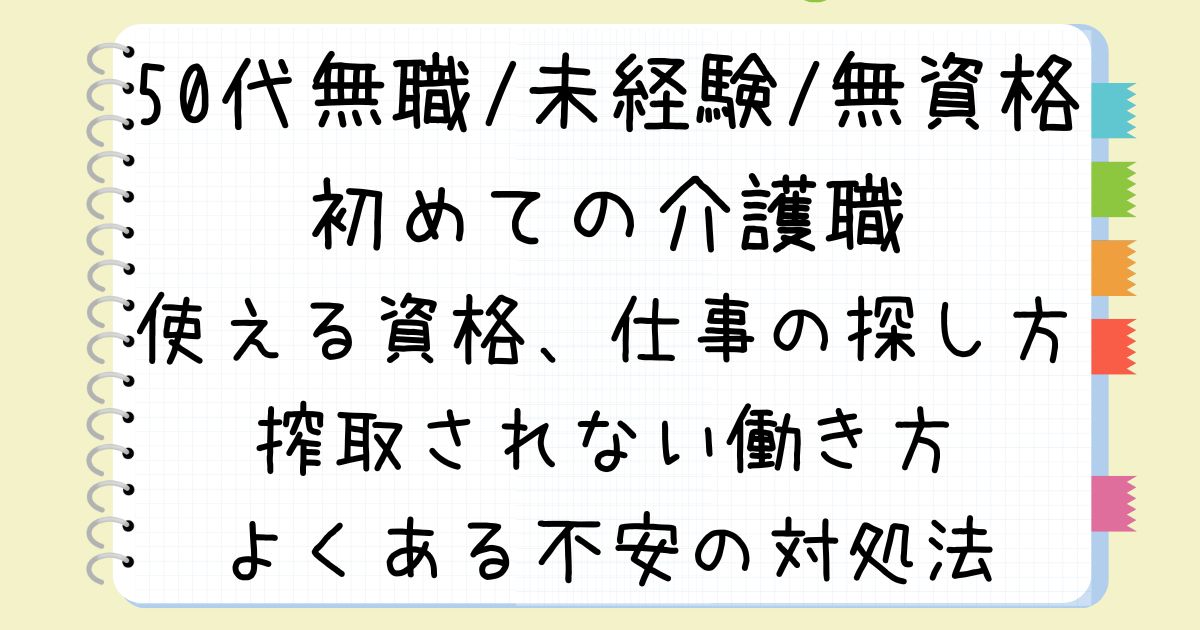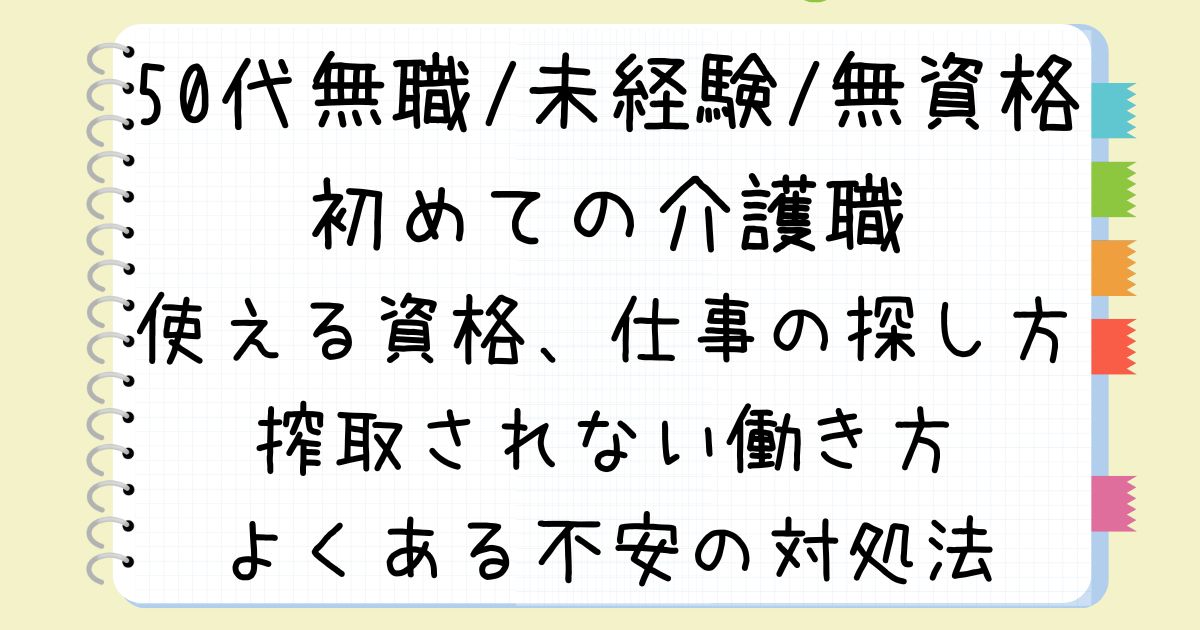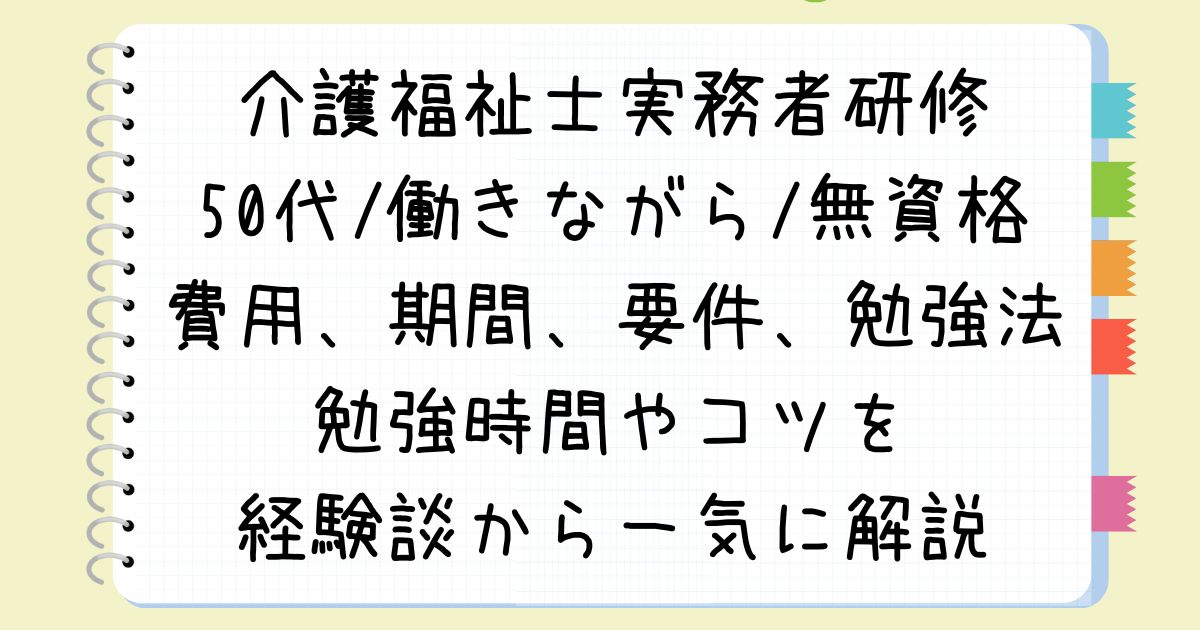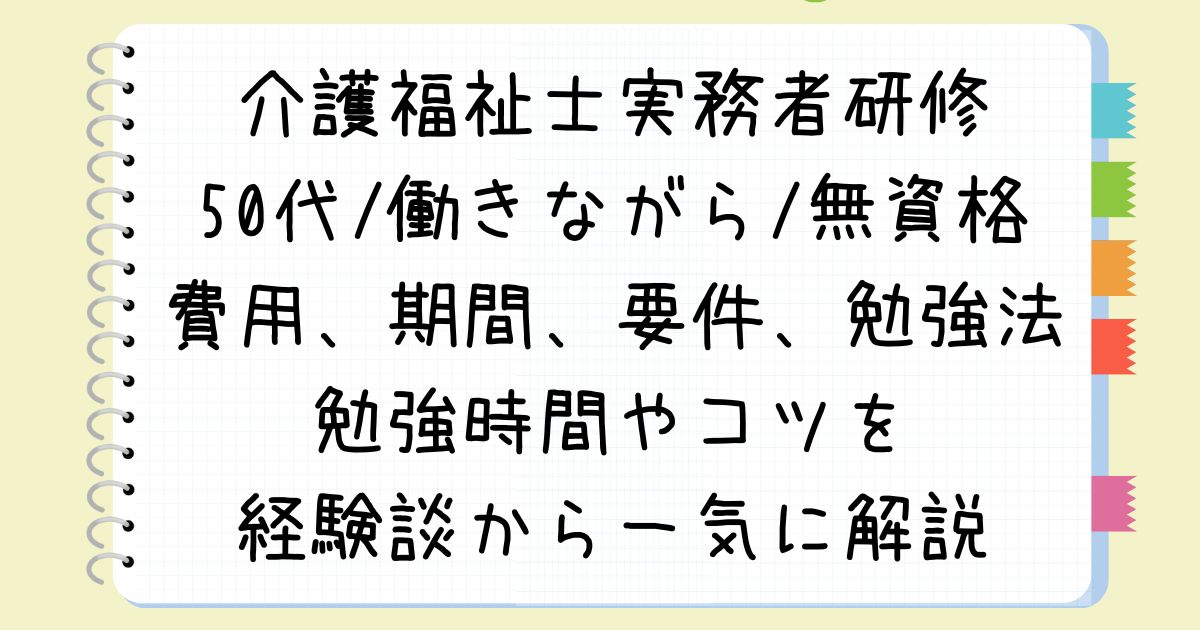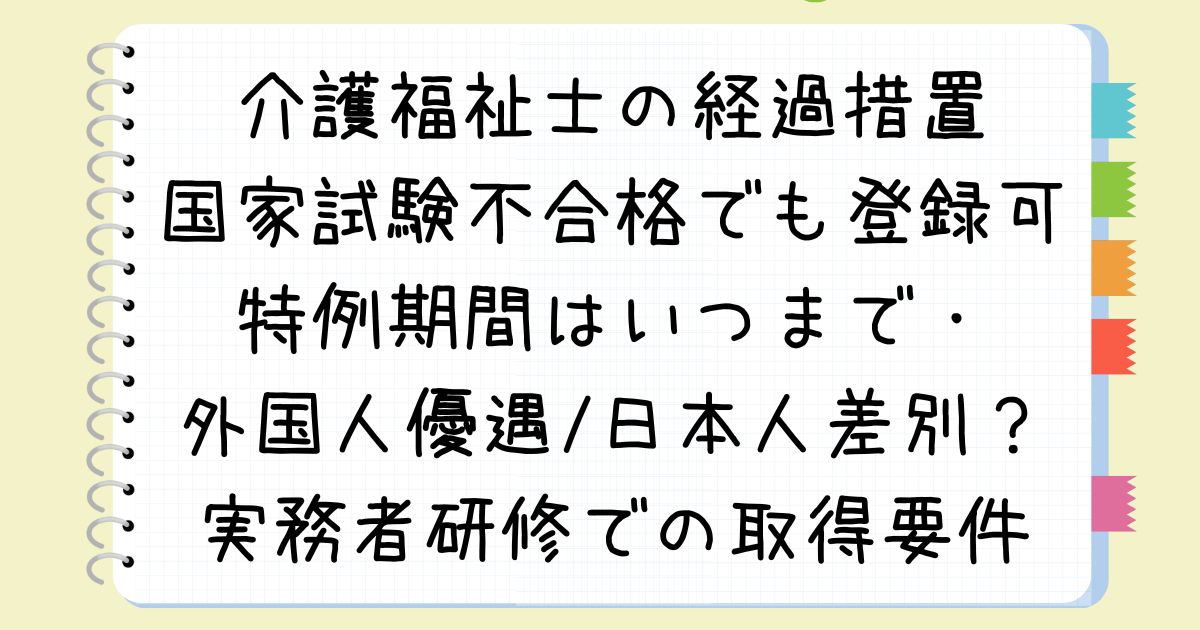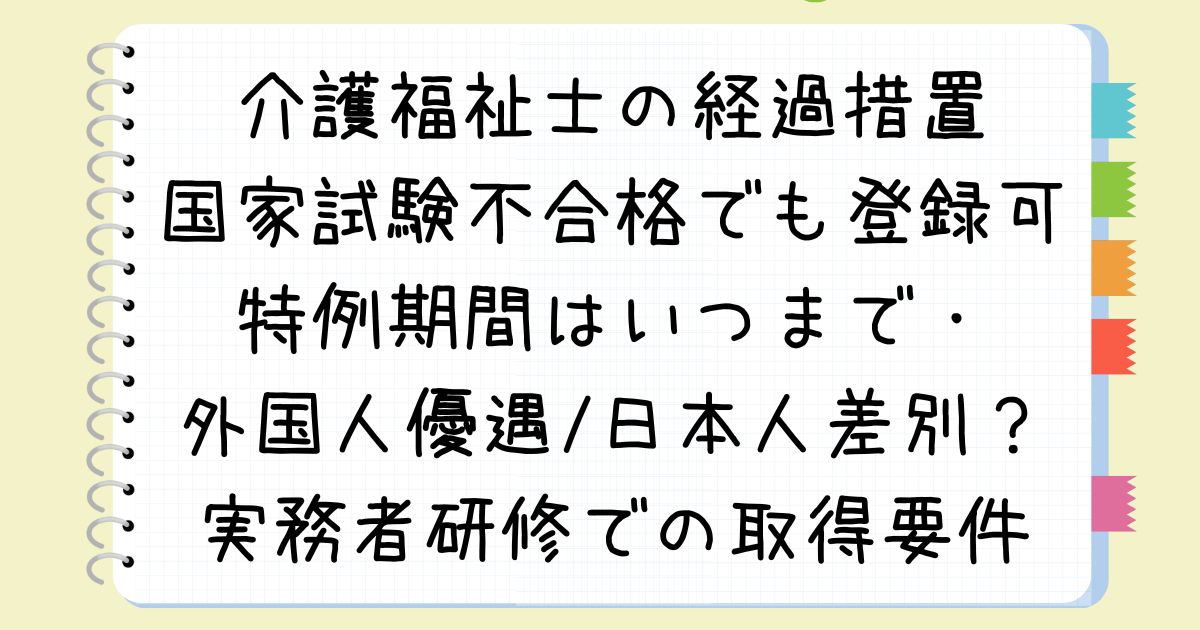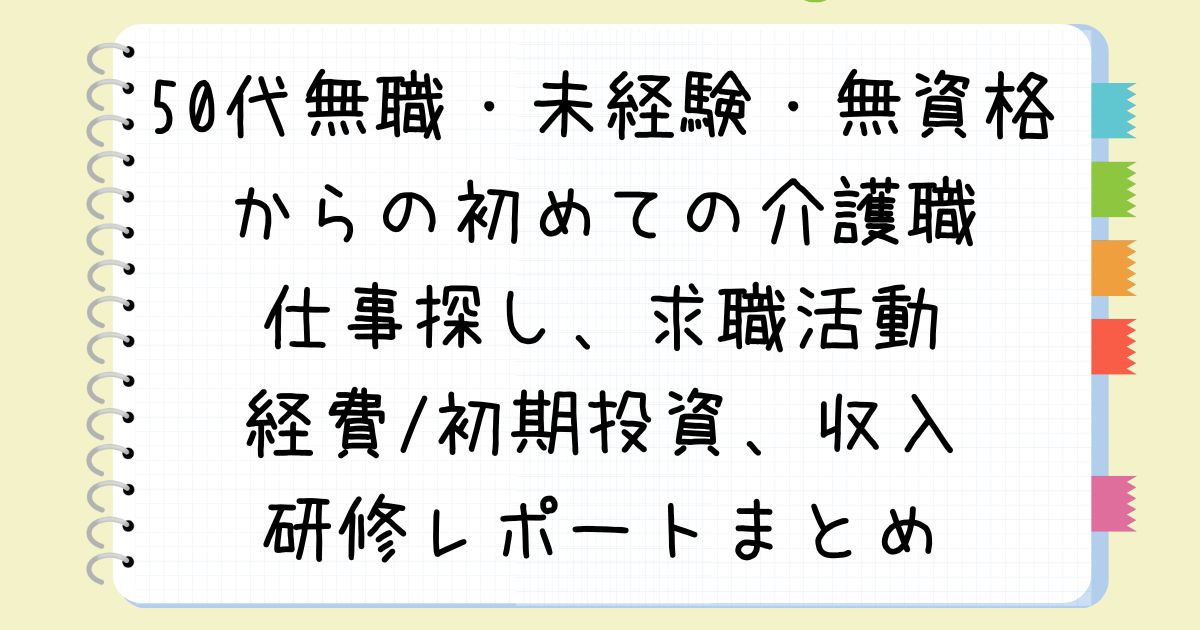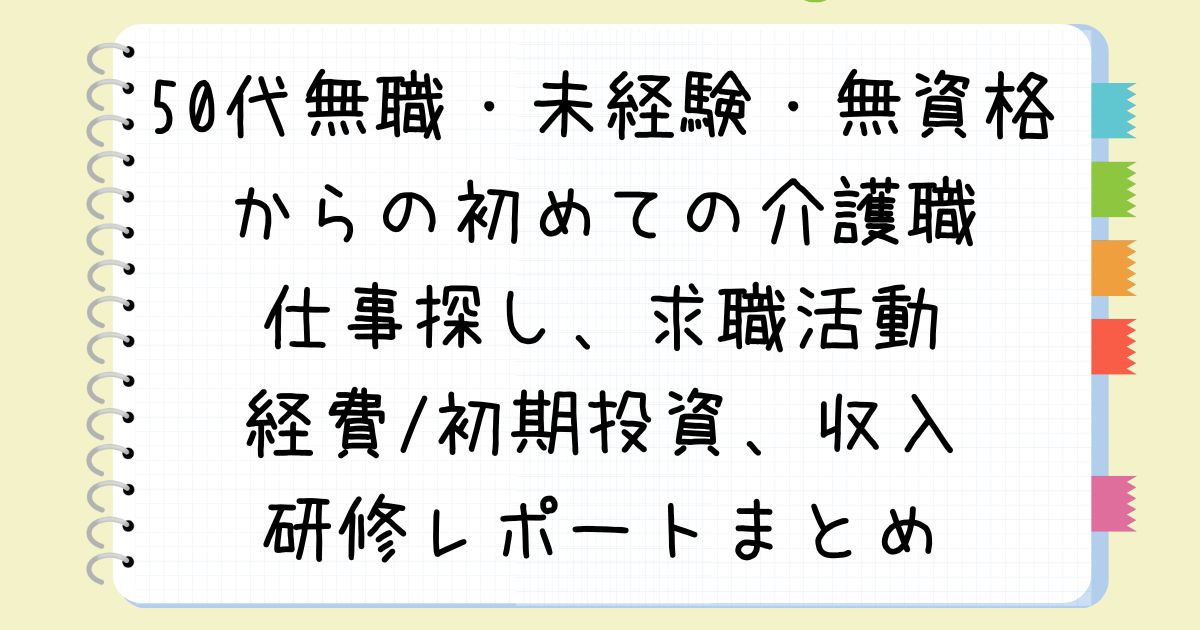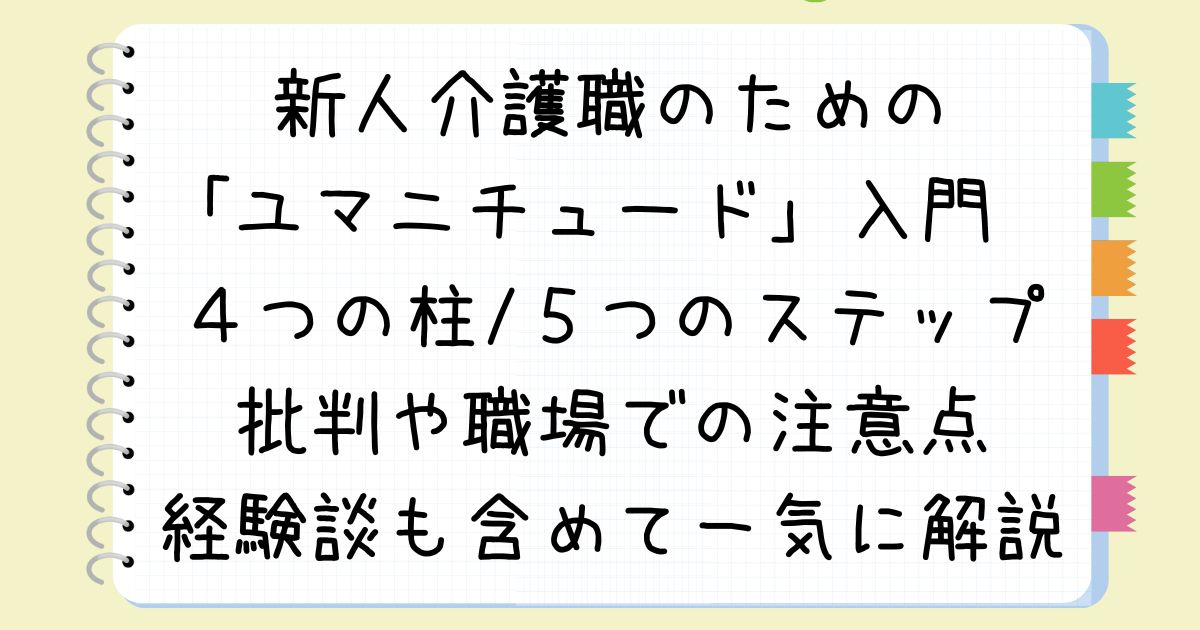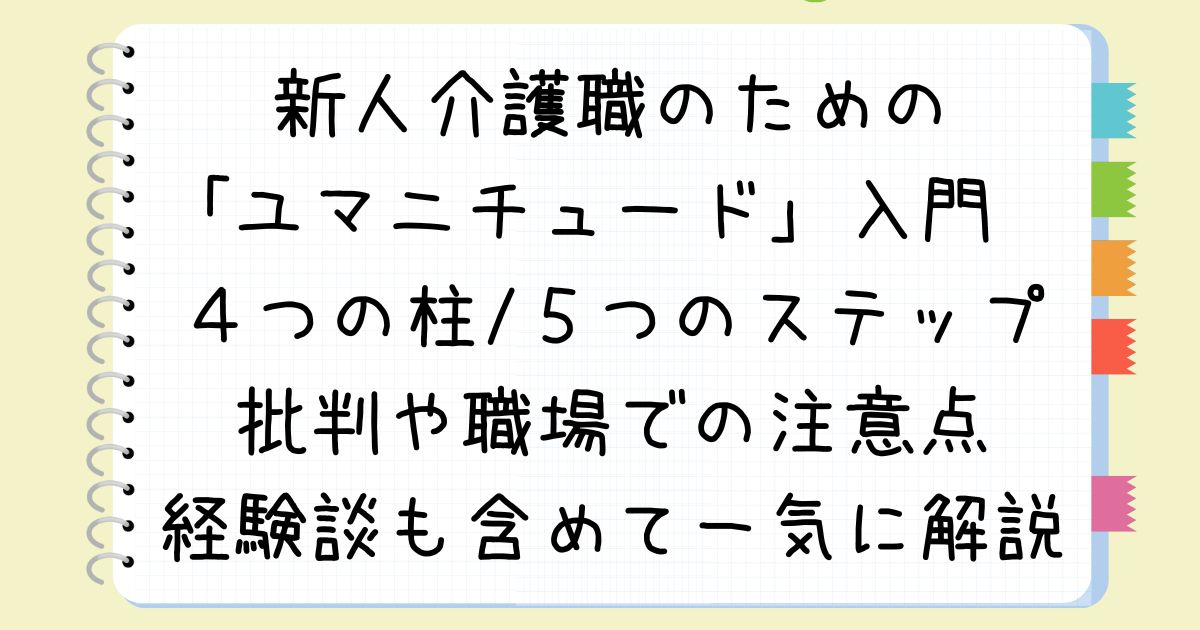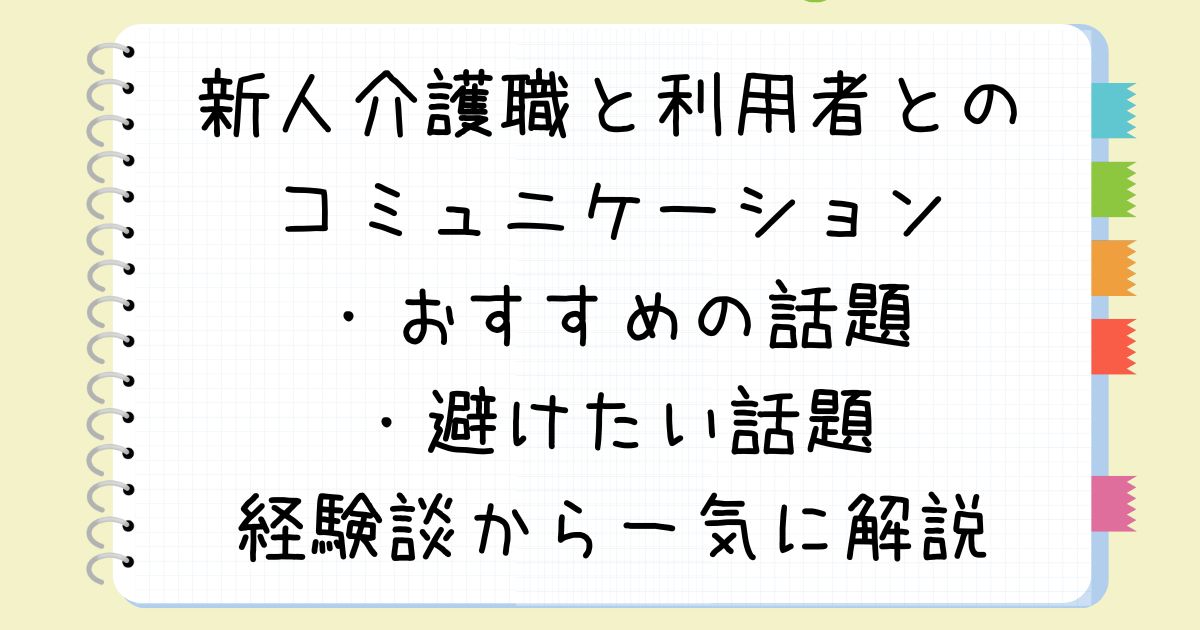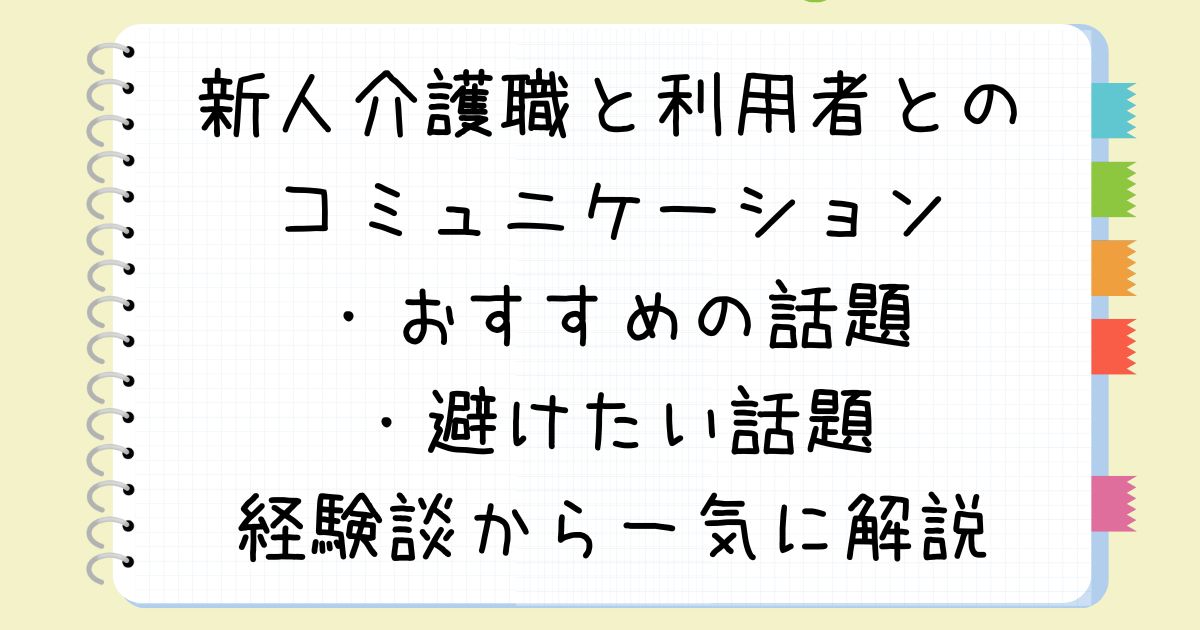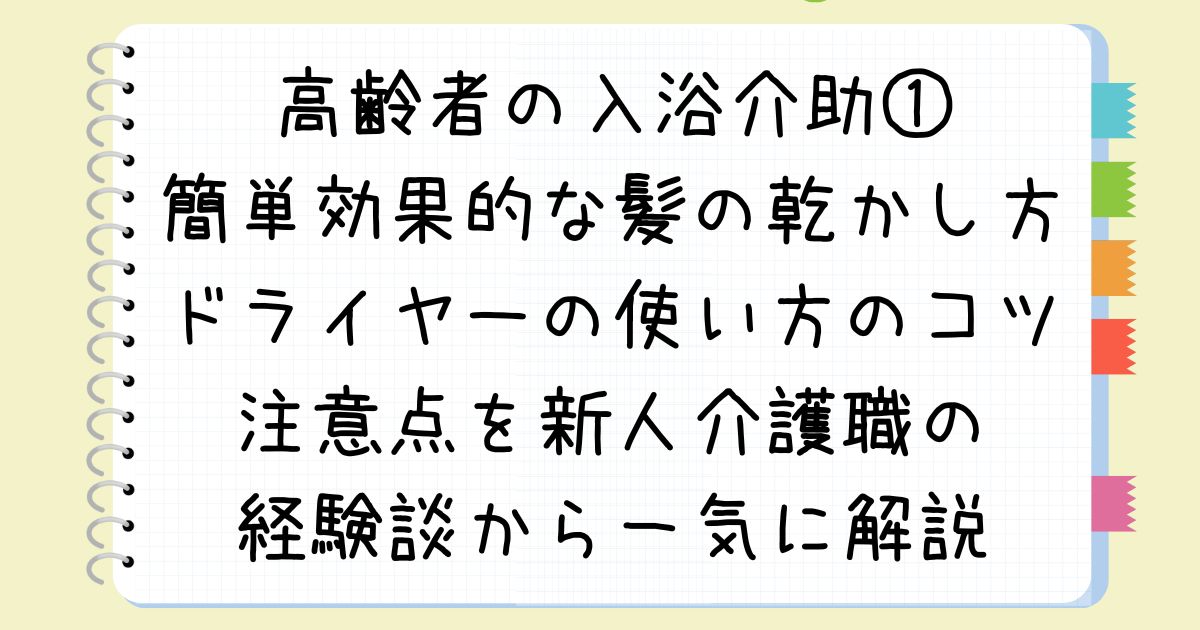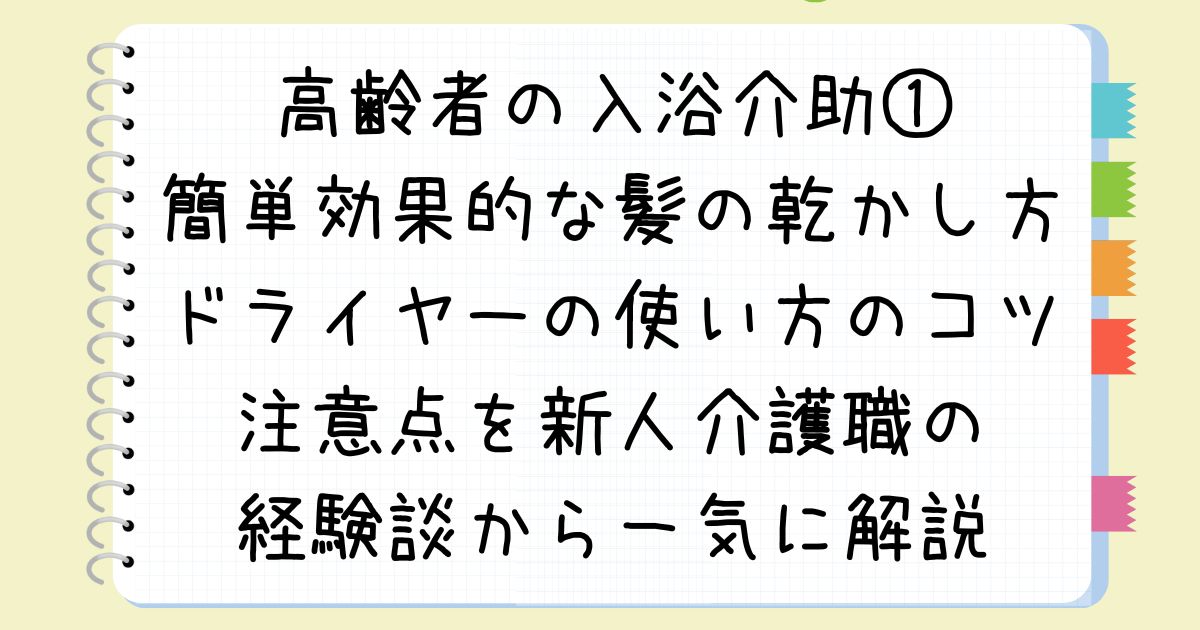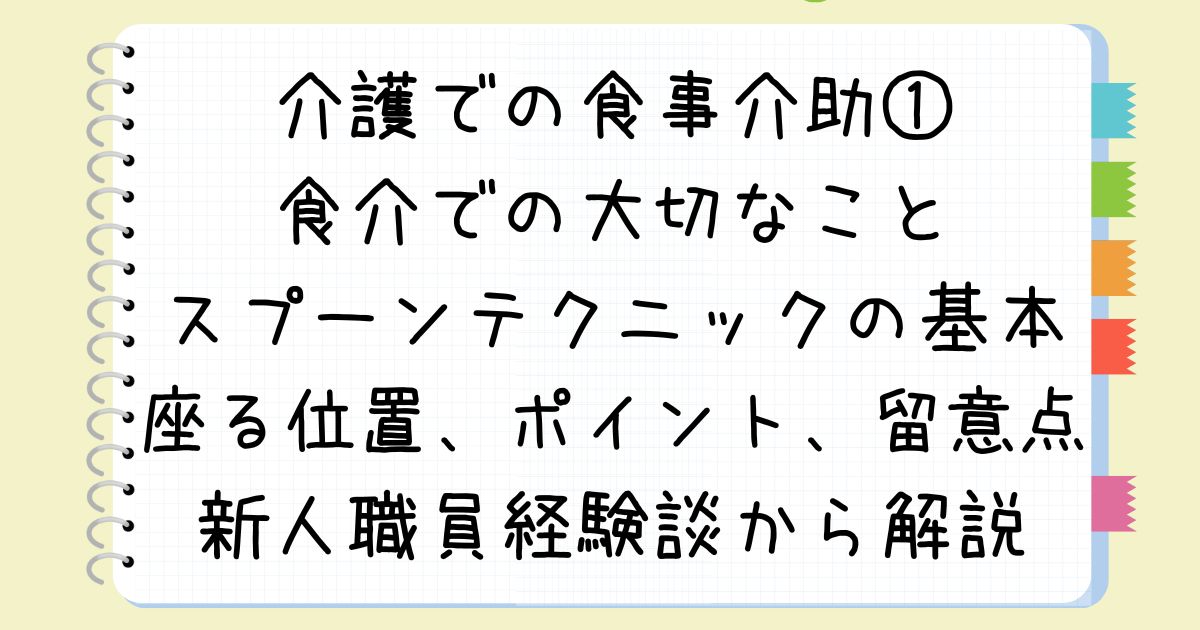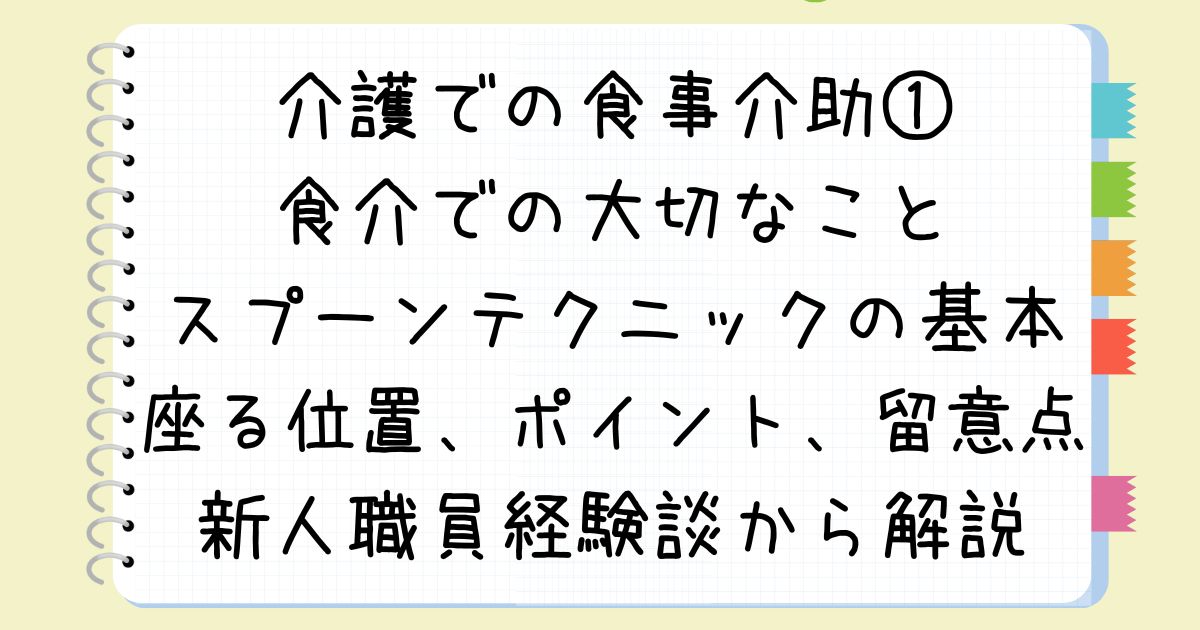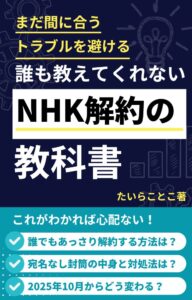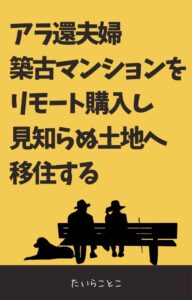無資格での介護職〜資格なしでもできる介護の業務内容/範囲、資格なしだと働けないは本当か、義務化された介護の研修、経験談
無資格で介護職員として働く場合の業務範囲や義務化された研修についてまとめておきます。
介護業界は無資格だと働けなくなるのは本当か
業務内容にもよりますが、無資格/資格なしでも介護業界で働くことはできます。ただし、無資格のまま働き続けることはできなくなりました。
これは、2024年4月から「認知症介護基礎研修」修了が義務化されたからです。無資格者の場合、入職後1年以内に受講する必要があります。

eラーニングで1日で修了できます。
認知症介護基礎研修・生活援助従事者研修とは
認知症介護基礎研修とは
認知症介護基礎研修は、認知症ケアに特化した入門的な研修です。2024年4月以降、介護職員には受講が義務付けられています。
【認知症介護基礎研修とは】
- 内容:認知症介護の基本的な知識や必要な技術の習得
- 受講対象者:介護関連の無資格者
- 受講方法:全編eラーニングや、集合型研修(講義+演習)
- 受講時間:1日で修了
eラーニング:約150分の動画視聴、復習問題や確認テスト
集合型研修:講義3時間+演習3時間程度 - 費用:5,000円程度
認知症介護基礎研修の受講対象者は、介護関連資格の無資格者です。実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者などは、受講不要です。
受講費用は自治体や主催者よって異なりますが、2025年度は5,000円程度です。事業所によっては、無料で受講できるサポートがあります。
資格なしでも認知症介護基礎研修が必須とは限らない
認知症介護基礎研修の受講対象者は、介護関連資格の無資格者です。資格なしの場合、入職から1年以内の受講が義務付けられてます。
ただ、現状「資格なし」でも、1年以内に初任者研修(介護職員初任者研修)や実務者研修(介護福祉士実務者研修)を修了予定であれば、受講不要です。



私は、実務者研修を受講しながら、現状無資格で介護施設でパート職をしています。面接時にその旨伝えていたので、「認知症介護基礎研修」の受講を勧められることはありませんでしたし、受講もしていません。
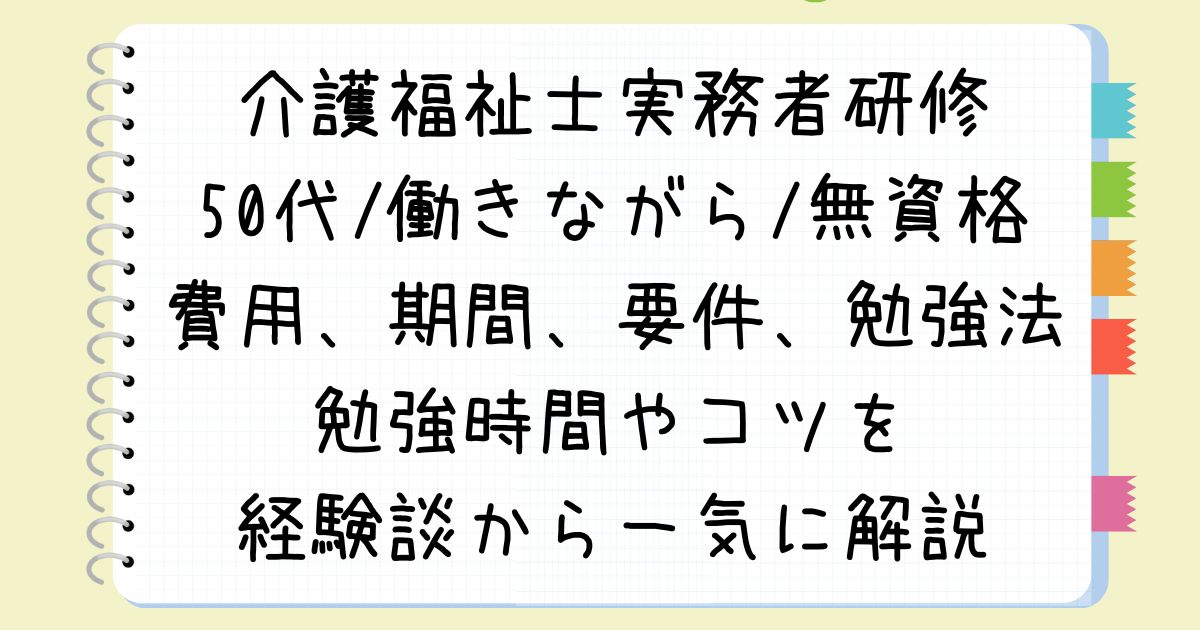
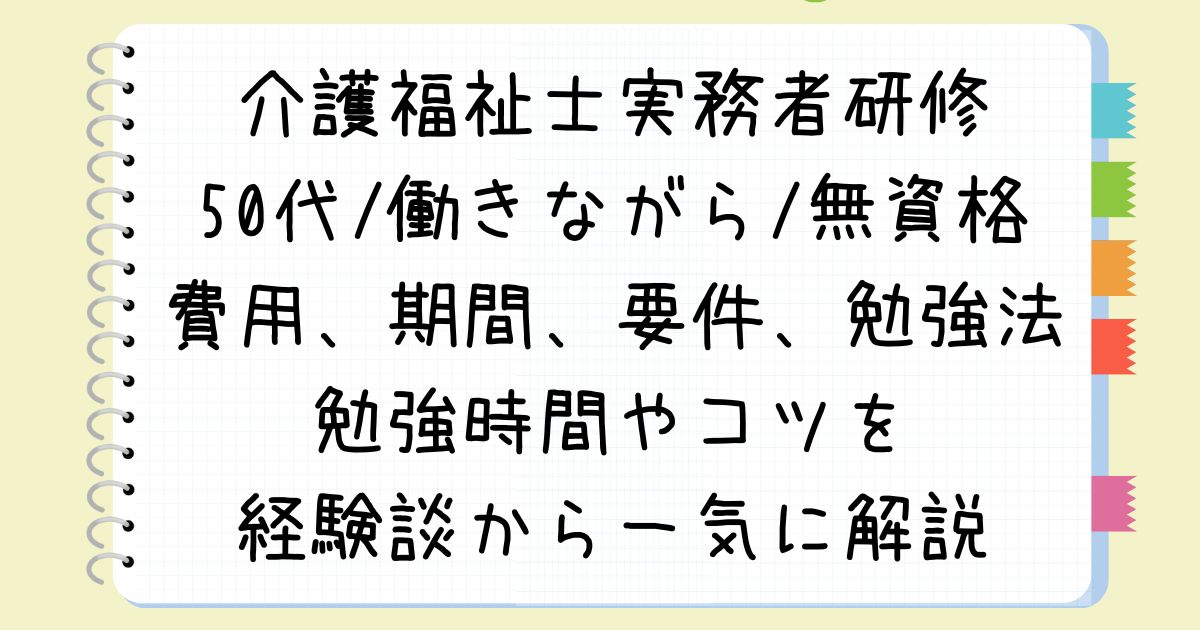
認知症介護基礎研修を修了したところで
認知症介護基礎研修を修了は、公的な「資格」の1つですが、修了したところで、待遇改善につながるかは微妙です。
中には、資格手当として多少の給与アップにつながる事業所もあるかもしれませんが、つながらない事業所もあります。
スキルアップや、給与アップを目指すなら、初任者研修や実務者研修を受講するのが最短確実な方法です。



私のパート先では、「認知症介護基礎研修」は資格手当の対象外。無資格と同格です。
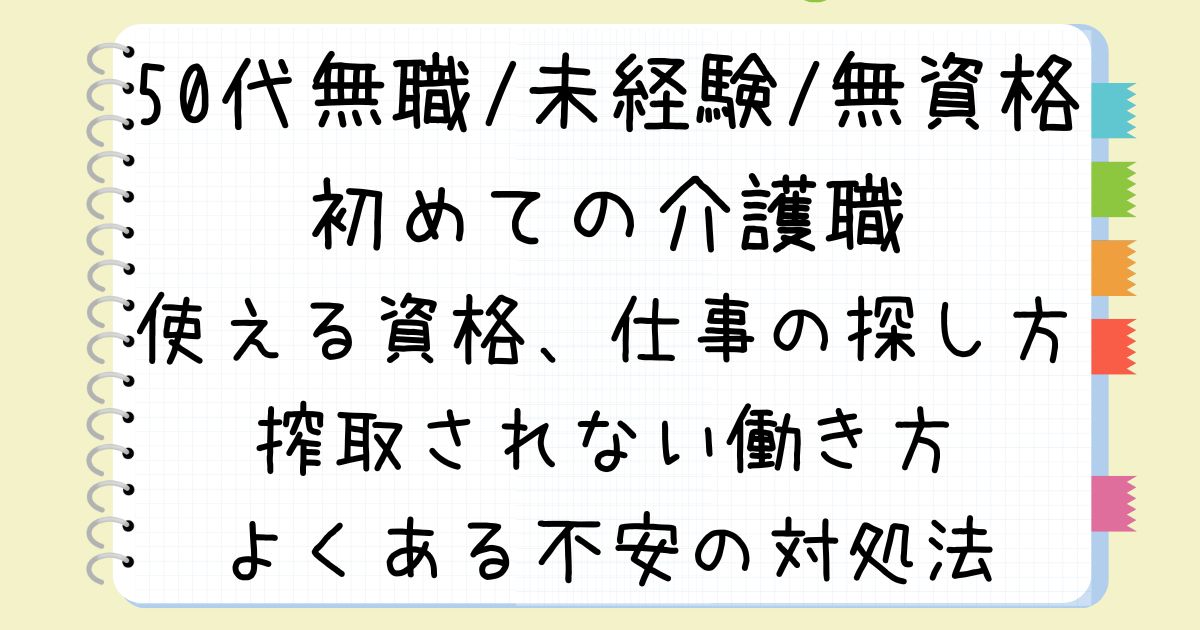
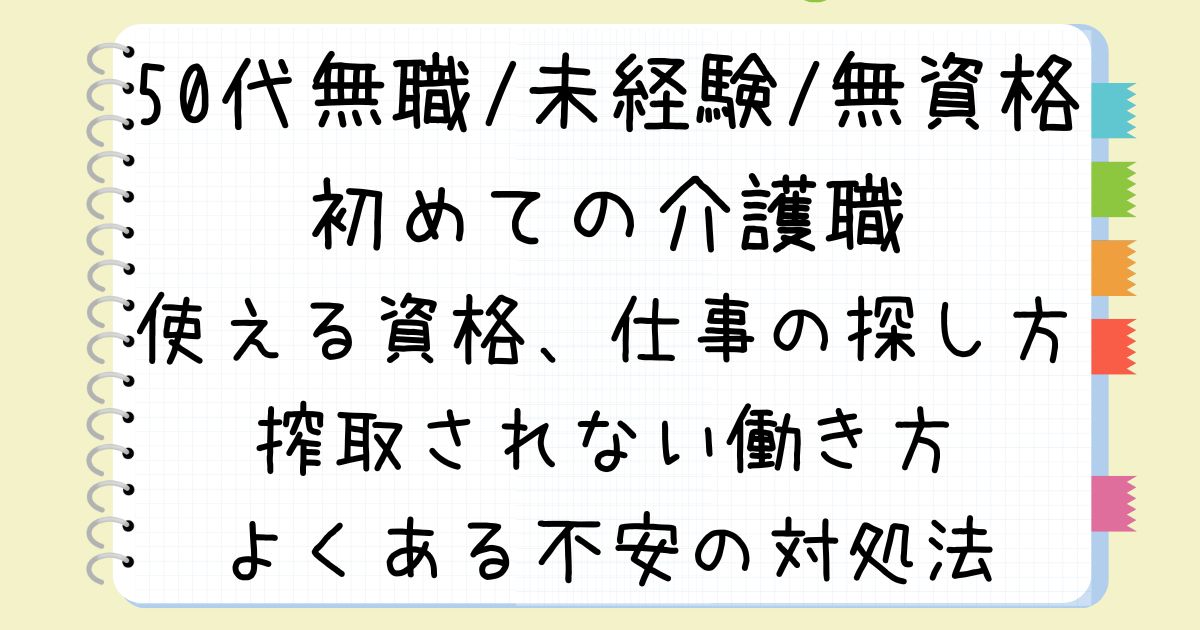
生活援助従事者研修とは
生活援助従事者研修は、生活援助業務に必要な幅広い知識と技術を習得するための研修です。
【生活援助従事者研修とは】
- 内容:訪問介護における生活援助サービス(調理、洗濯、掃除、買い物など)に必要な基本的な知識と技術の習得
- 受講対象者:介護関連の無資格者
- 受講方法:集合型研修(講義+演習)や通信型研修(通信+講義+演習)
- 受講時間:59時間程度
移動・移乗関連の実習2時間程度含む
通信教育など自宅学習できるのは29時間 - 費用:無料〜3万円程度
生活援助従事者研修の受講対象者は、介護関連資格の無資格者です。
資格なしで介護の生活援助に従事する場合、受講することが望ましいようですが、2025年現在、受講の義務づけはありません。また、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者などは、受講不要です。
受講費用は自治体や主催者よって異なります。自治体や事業所によっては無料で受講することも可能です。資格スクールなどで受講する場合には、消費税やテキスト代を入れると3万円程度かかるようです。
事業者に聞くか、「生活援助従事者研修 自分の住んでいる都道府県名」で検索すると、自治体の情報を確認することができます。
認知症介護基礎研修・生活援助従事者研修の違い
| 項目 | 認知症介護基礎研修 | 生活援助従事者研修 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 認知症ケアの基礎知識・技術の習得 | 生活援助サービスの基礎知識・技術の習得 |
| 対象業務 | 認知症の方への介護全般 | 生活援助 *身体介護は含まない |
| 必須性 | 介護施設で働く時には必須 *介護の上位資格保持者は免除 | 必須ではない |
| 研修内容の焦点 | 認知症の理解と対応 | 生活援助技術、高齢者・障害の基礎理解 |
| 研修時間 | 数時間~1日程度 | 59時間程度 |
| 修了後の業務範囲 | 生活援助、身体介護(施設内のみ)、送迎業務等 | 生活援助 |
介護資格なしでできること・できないこと
介護関連の仕事では、介護資格なしでできることと、できないことがあります。
介護資格なしでもできること


身体介護(施設内のみ)
身体介護とは、介護が必要な利用者の身体に直接触れて行うものです。
「三大介護(三大介助)」と呼ばれる食事介助・入浴介助・排泄介助の他、ベッドや車椅子の移乗介助、歩行介助などがあります。
介護施設や事業所に配置される介護福祉士の指示のもとであれば、無資格者でも身体介護を行うことができます。



現状無資格の私も、パート先では身体介護をしています。
施設や事業所によるかと思いますが、介助の際に口頭で説明されて、次からよろしく、わからないことは聞いてね、みたいな感じ。それどうよ…とは思いますが、そういうものらしいです。
知識や演習経験もほぼないし、当然に資格手当もないのですから、業務内容を分ける方が正しいように思いますが、、そこに正義はありません。
施設や事業所によっては、無資格者には身体介護をさせず、業務を明確にわけているところもあります。
無資格・未経験から介護施設で働く場合、移動介助、立ち上がりや座る際の介助、移乗介助だけでも、少し頭に入れておくと心の準備ができます。オススメ↓ Kindle Unlimited対象、無料で読めます。



無資格・未経験なので、職場で他の職員から直接教えてもらうまでは、一切の身体介護はしませんでした。今日は移動介助、今日は排泄介助、今日は移乗介助、、のように、実際の介助の際に、横につき教わりました。
といっても、実演見本は基本1回、次からよろしく、、といった扱い。メモはとりますが、家では上の本(安全・やさしい介護)で復習。次の勤務直前に、再度復習。
実務者研修のテキストよりもわかりやすいです。
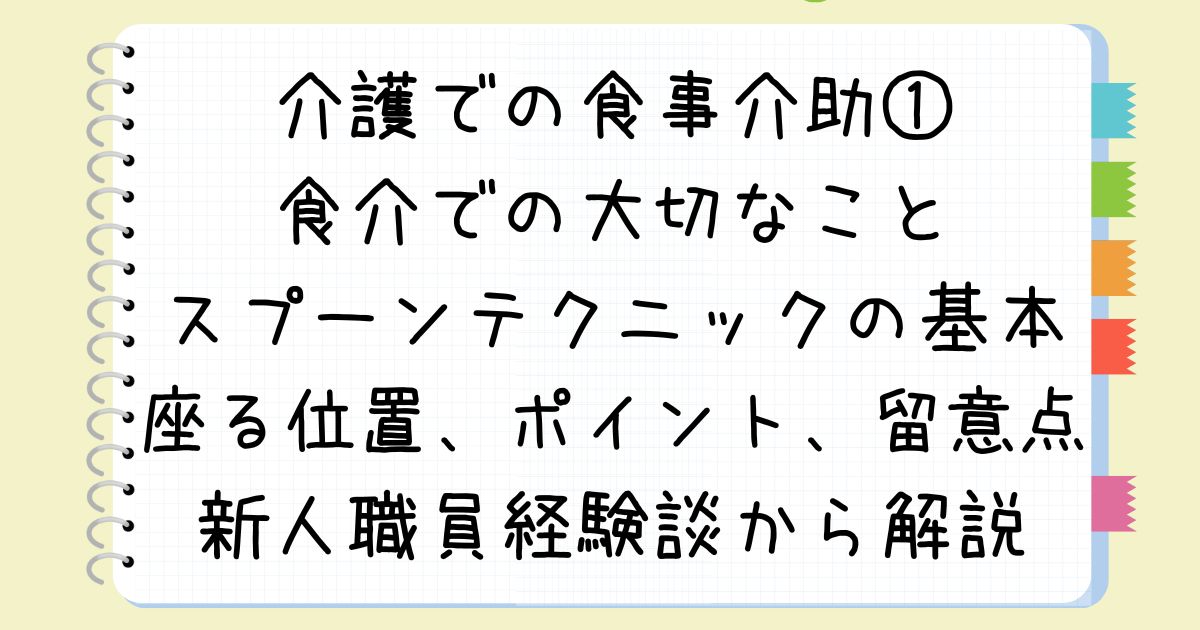
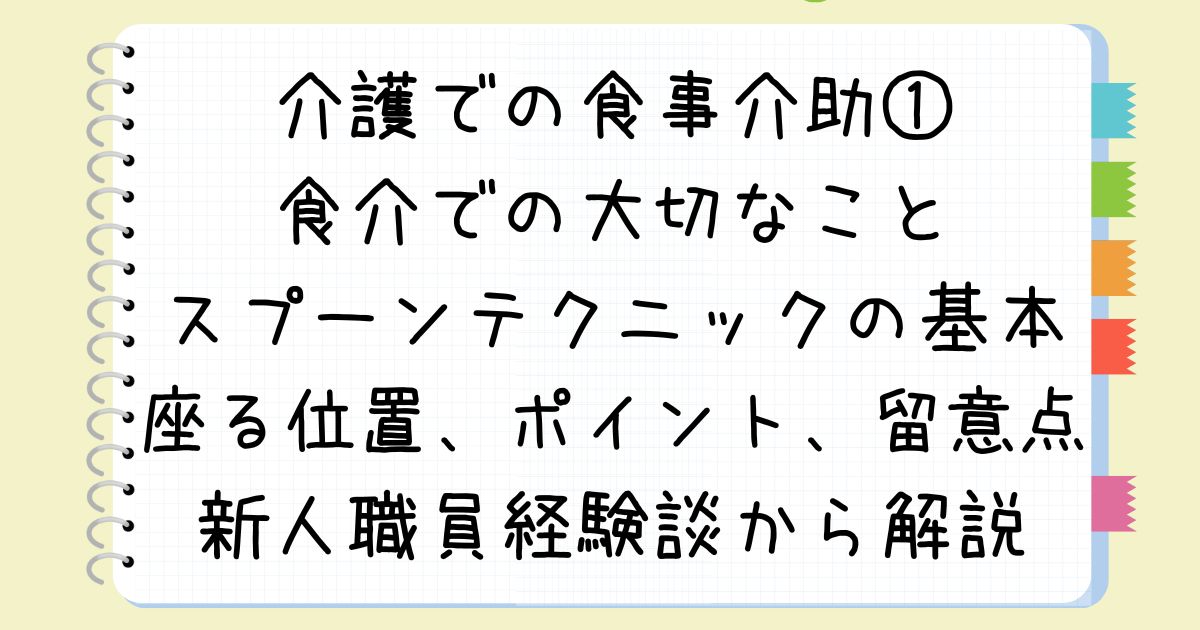
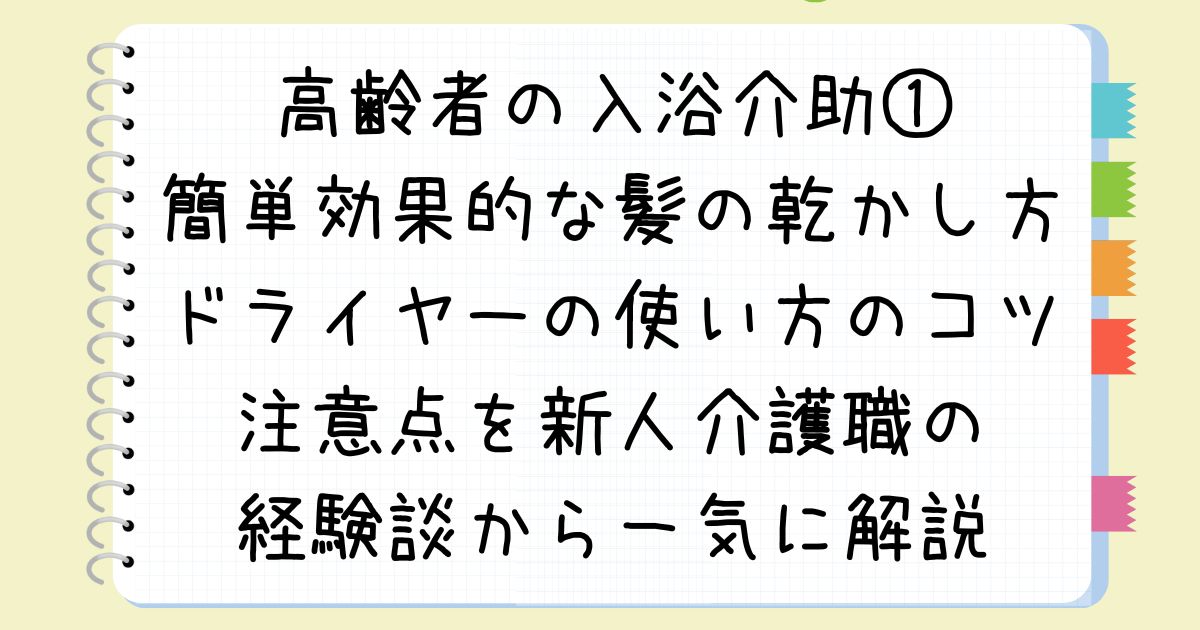
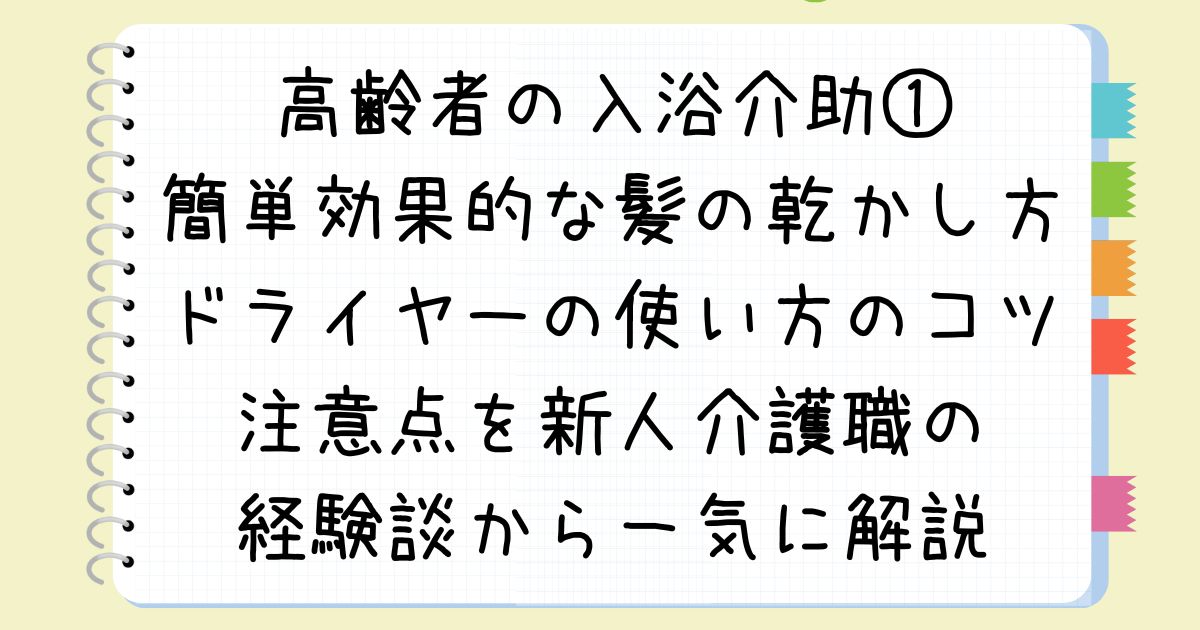
生活援助
生活援助とは、利用者の身体に触れずに行う日常生活のサポート業務です。
主に、食材や日用品の買い物、居室内やトイレの掃除、洗濯、調理・配膳などがあります。
送迎業務
利用者が自宅から通い、介護サービスを受けるデイサービスやデイケアなどの通所型施設の場合、利用者の送り迎えをする送迎業務は、介護の資格がなくても可能です。
車への乗降時に介助が必要になるため、事業所や施設によっては、介護職員初任者研修等の修了が必要な場合もあります。送迎業務は、第1種運転免許で対応可能、第二種運転免許は不要です。
事務作業
介護施設では、利用者をサポートする現場の介護業務の他にも、さまざまな事務作業作業があります。施設の受付や電話対応、備品の発注・管理、レクリエーションの企画・準備など。
これらの業務は無資格でもできます。



私のパート先では、
◼︎施設の受付や電話対応:
事務室や職員(正社員の介護福祉士等)が担当
介護福祉士の資格をもつパート従業員もいますが、その人たちも電話対応などはしません
◼︎備品の発注や管理:
職員(正社員)が担当
パート組は、在庫が少なくなった時点で報告
◼︎レクリエーションの企画・準備:
正社員・パート・有資格・無資格関係なく全員で行います
介護資格なしではできないこと
介護資格なしの場合、「訪問介護において直接身体に触れる身体介護をすること」はできません。
訪問介護は、基本的に一人で行うので、無資格者が有資格者の指示で指導や監督のもと身体介護を行うことができないからです。
【訪問介護で身体介護ができる主な資格】
- 介護福祉士
- 介護福祉士実務研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者
- 旧介護職員基礎研修修了者
- 旧訪問介護員(ホームヘルパー)1級または2級課程修了者
訪問介護の初心者研修の1つに「生活援助従事者研修」があります。
ただ、生活援助従事者研修を修了しても、可能な業務は生活援助のみ。身体に触れる身体介護をすることはできません。給与面でも、資格手当がつくかは事業所次第です。
修了することで、訪問介護の基礎知識を習得することができますが、業務内容も待遇も無資格者と同じです。
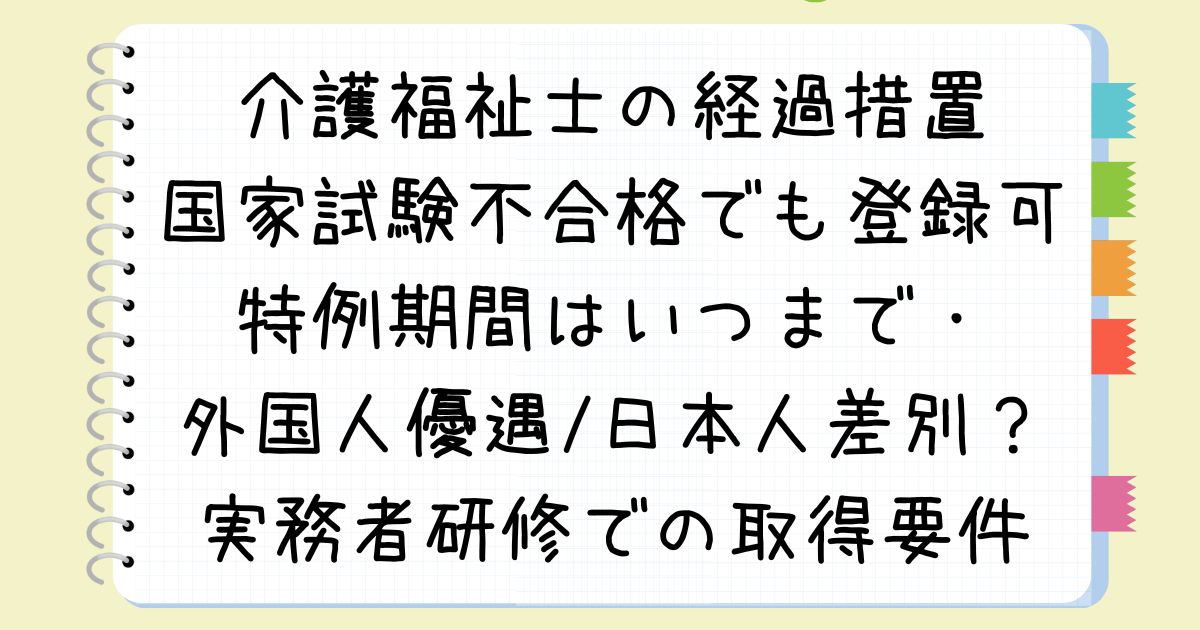
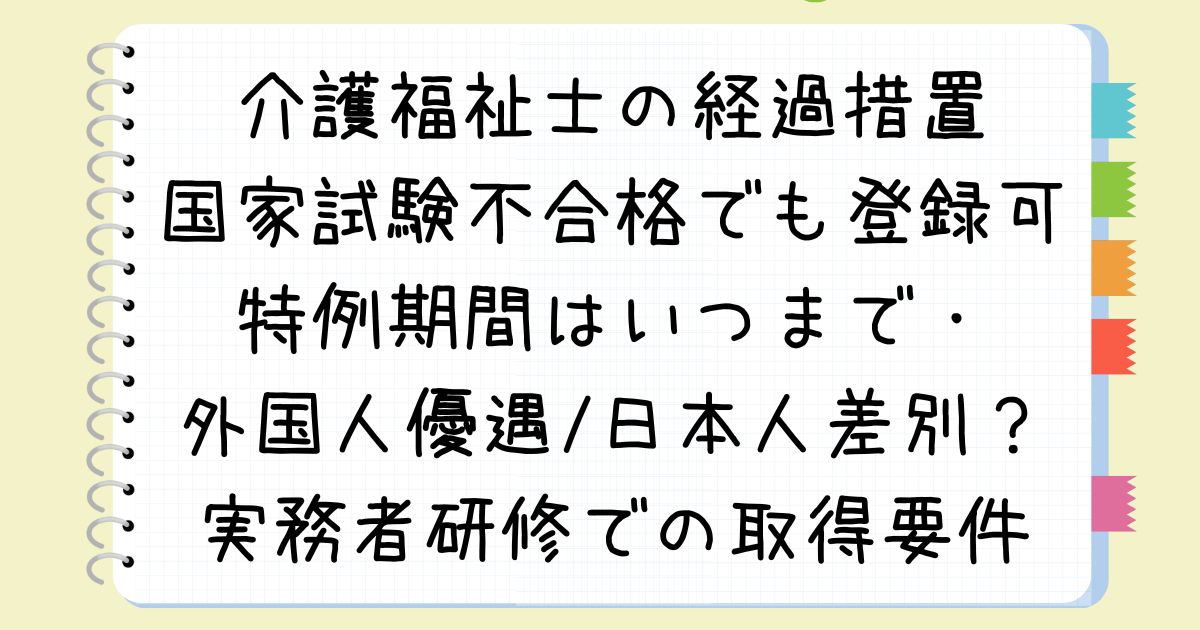
介護資格があってもできないこと
医療行為全般
喀痰吸引、経管栄養などの医療行為は、介護資格があってもできません。
医療行為に該当しない体温測定や自動血圧測定器による血圧測定、医師の指示や薬剤師・看護師等の指導を受けての服薬介助・軟膏塗布・点眼・湿布貼付などは、介護職員でも対応可能です。
出典:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)〔保健師助産師看護師法〕/厚生労働省
訪問介護〜介護保険適用外のサービス提供
訪問介護の場合、介護保険適用外のサービスの提供もできません。
これは、介護保険が適用される訪問介護は、あくまで利用者の生活援助であり、家事代行サービスではないからです。
【訪問介護でできないことの例】
- 車の運転の代行
- 家族分の買い物や家事援助
:同居する家族の洗濯、調理、買い物、掃除など
:本人が使わない部屋やベランダや庭の掃除など
:自家用車の洗車や清掃など - 散歩や趣味のための外出介助
・嗜好品やデパートへの買い物、美容室などへの付き添い - 行事食など手間をかけて行う調理
- 大掃除、床のワックスかけ、家屋の修理、家具の移動や修繕など
- 金銭の管理や契約書の記入などの手伝い
介護資格なしや未経験だと介護職は大変なのか
そもそも、それは愚問
「介護資格なし・未経験で介護職は大変なのか?」
無資格・未経験から介護職で働く時に気になりがちですが、控えめにいっても愚問です。
介護職に限らず、未経験の仕事は慣れるまで大変です。経験のある業種でも、職場ごとのルールやマニュアルがありますから、やはり大変です。
介護職だけが特別大変なわけでも、キツイわけでもありません。お金をもらって仕事をするということは、いつだって、どんな業種だって、それなりに大変なのです。要は、気にすることではない、ということです。
介護職は覚えることが多くで大変
介護職に従事する上で大変と感じていることの一つに「覚えることが多い」があります。
まず、入浴・排泄・移動・移乗・食事の介助のように、介護職の基本として習得しておくべきこともあります。
他に、利用者の顔・名前・個別ニーズ、施設内での活動に関わる作業(準備/片付けなど)、施設独自のローカルルールなど、覚えることはたくさんあります。
これは、マニュアル/手順書を確認したり、メモをとって作業のたびに確認する、復習して覚える、などするしかありません。



覚えることは、時間と経験が解決してくれます。
私は、無資格・未経験、しかも週2回短時間勤務のパートですから、慣れるまでに時間もかかります。不慣れな作業でスピーディに対応できず、職員からの風当たりが強く感じられることもありますが、気にしないようにしています。
言い訳のようですが、週2日勤務ということは、週5日勤務の人と比べれば、同じ経験を積むまで単純計算で2.5倍の期間がかかります。
2ヶ月勤務しても86時間程度(5H/日×2日/週×4.3週×2ヶ月)。週5日勤務する人の1月分にもなりません。
ですから、1〜2ヶ月程度の勤務で、わからないことを無くせとか、もっとスピーディーにとかは、所詮無理な話。
謎に「頑張りましょう」「覚えてください」「やってください」的圧をかけられていますが、程よくスルーしています。
ただし、
・同じ失敗を繰り返さない
・できるだけ1度で覚える
・わからないことは迷わず聞く
・できないことは無理をしないで他の職員にお願いする
などのように、自分でできることはしています。
体力的な負担が大きい
介護の現場では、移動/移乗/入浴/排泄介助など、利用者の身体介護があるため体力的負担がかかります。
施設によって、利用者の介護度数に差がありますので、不慣れなうちは介護度数の低い傾向にある施設を選ぶのもコツです。
【介護度数が低めの施設】
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- デイサービス(通所介護)
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)



施設によっては夜勤もあります。無資格の場合は、夜勤なしのこともあります。
介護に関わらず夜勤経験がない方は、夜勤は少し慣れてからの方がいいかもしれません…
コミュニケーションが難しい
認知症や聴力の低下などの理由から、利用者とのコミュニケーションに難しさを感じることもあります。
他の職員の様子をみたり、コツを教わったりしながら、何度もコミュニケーションをとってみるしかありません。
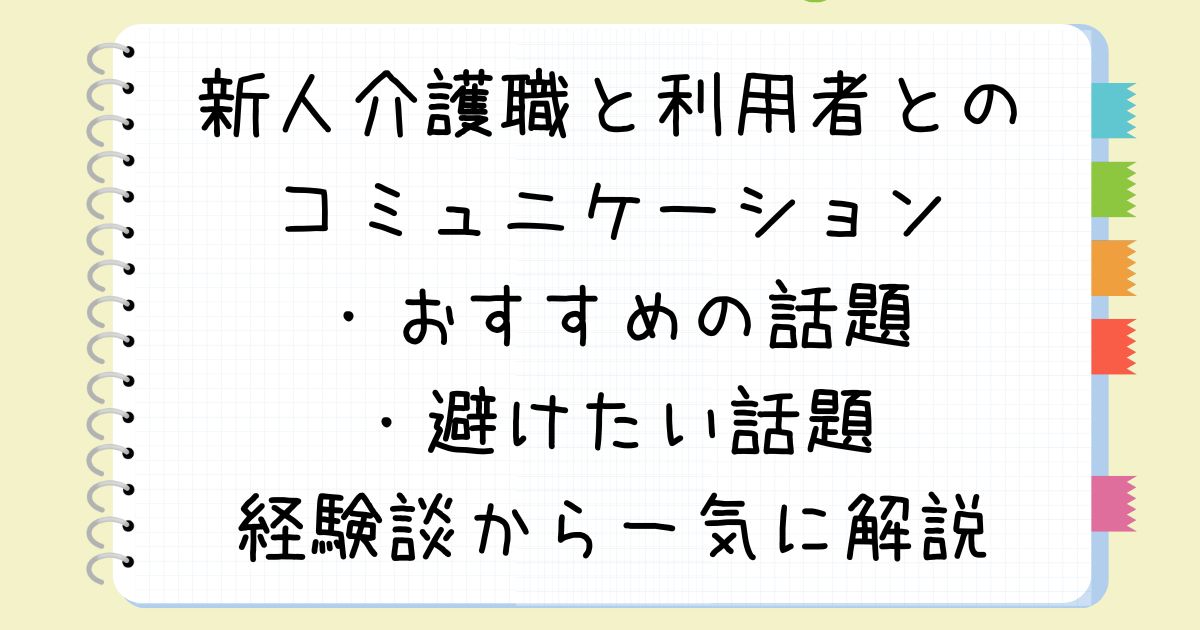
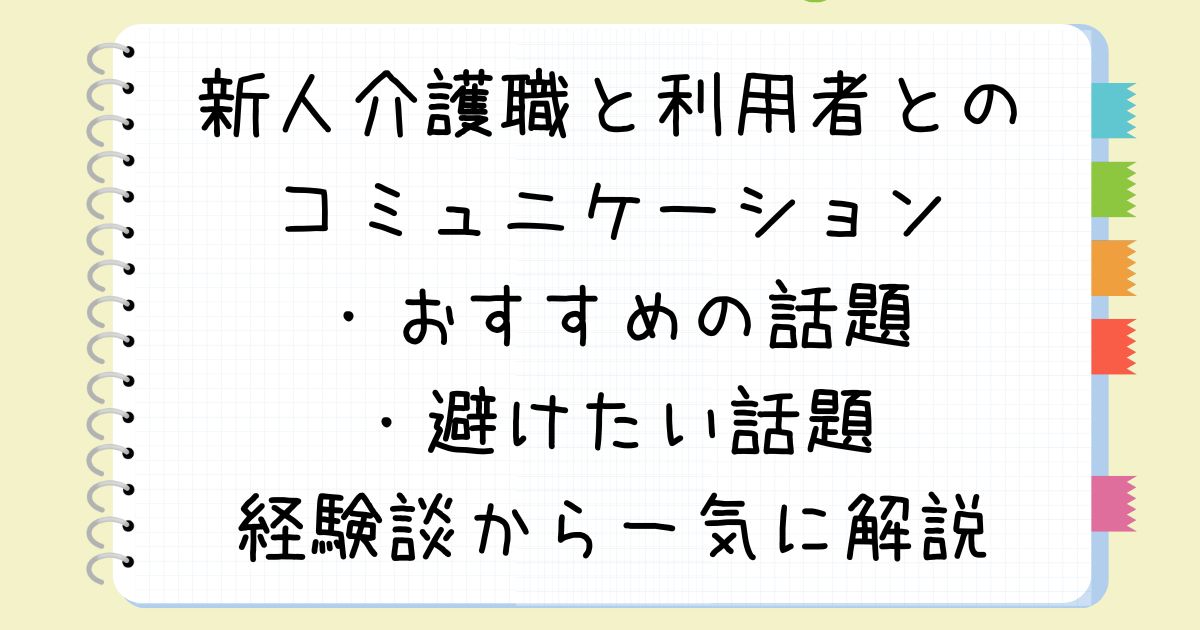
コミュニケーションをとりにくい方との接し方、心構えなどの参考になります。ぜひ一読を!↓



本から学んだことを、できる範囲で取り込んで介助するのがおすすめです。
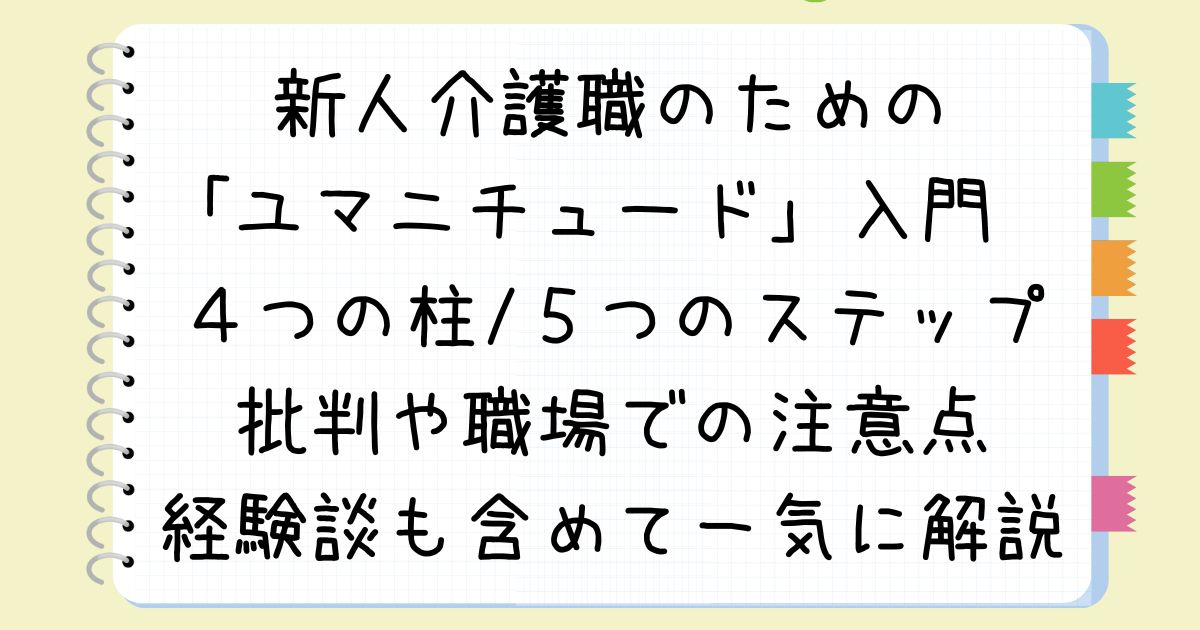
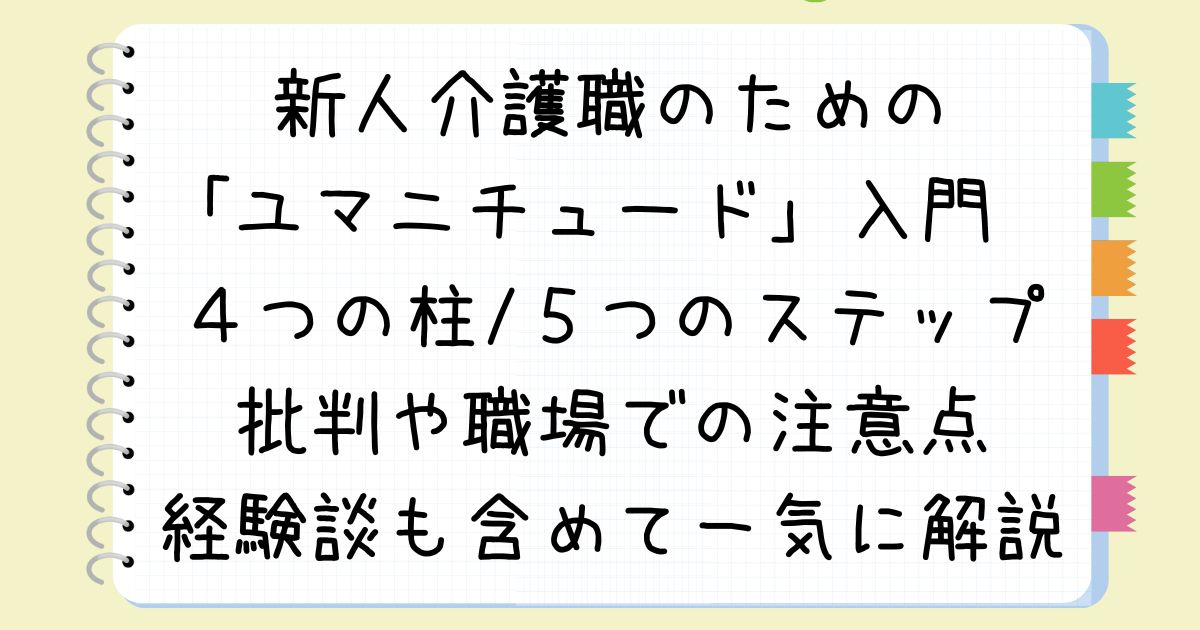
人間関係が難しい
介護の現場は、小さくて密度の高い縦社会のようなものです。
人間関係がうまくいけば楽しい職場になる可能性もありますが、うまくいかないと感じると働くこと自体がストレスで苦痛になります。
あくまでも「職場」であると割り切って、業務に関わるコミュニケーションにとどめ、人間関係に深入りしないことをオススメします。
入職時は、珍しさもあって色々聞かれたりしますが、差し支えない程度にふんわり曖昧に答えておけばいいと思います。そして、自分の他の職員のことは詮索しない、話題は業務に関わることだけにする、噂話はしない、などの線引きをしておくと安心です。



職員が少ないとより濃密な関係になりやすいです。
一度深入りすると抜け出すのも大変ですから、入職時から程よい距離感を持っておくのがオススメです。
私は短時間パートなので、最低限の関わりしか持たないように気をつけています。