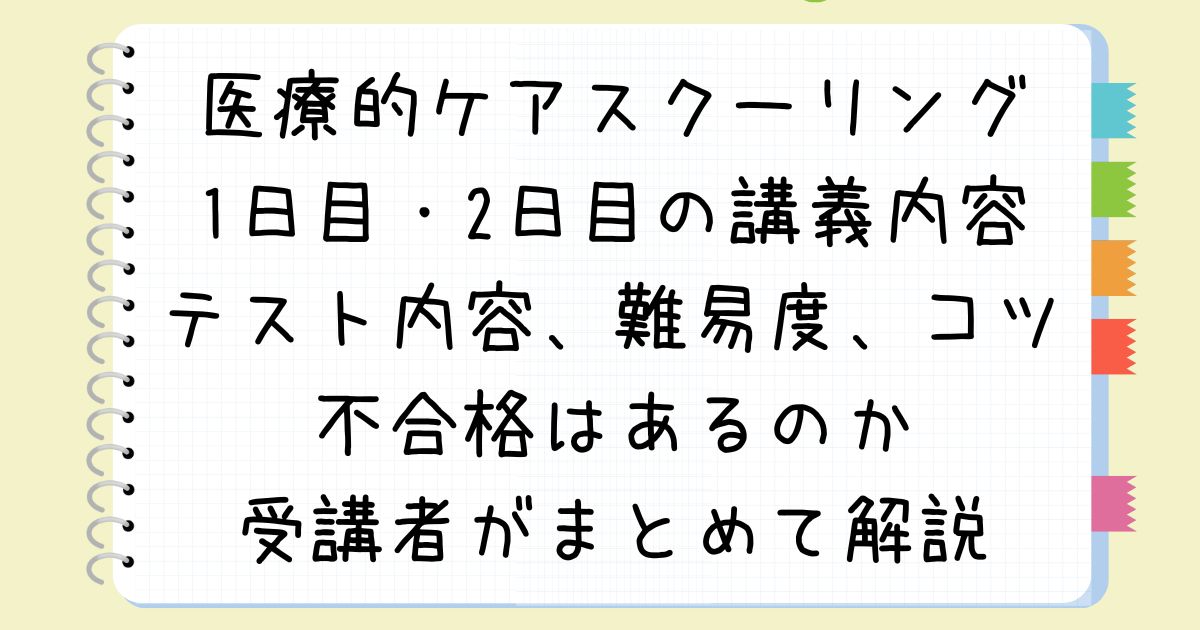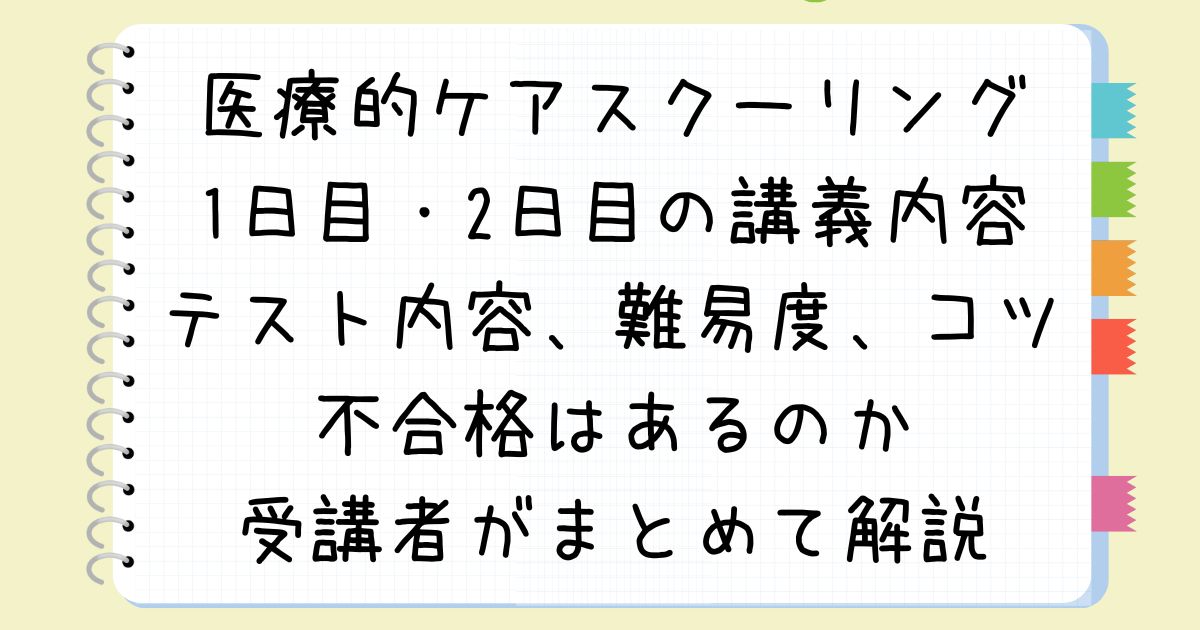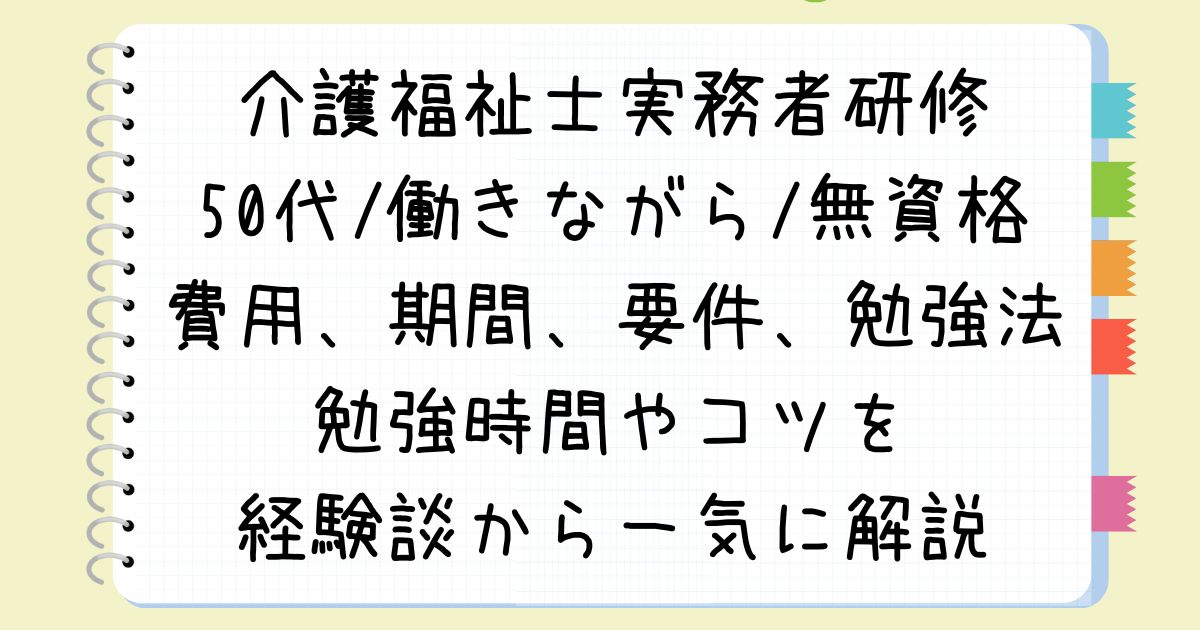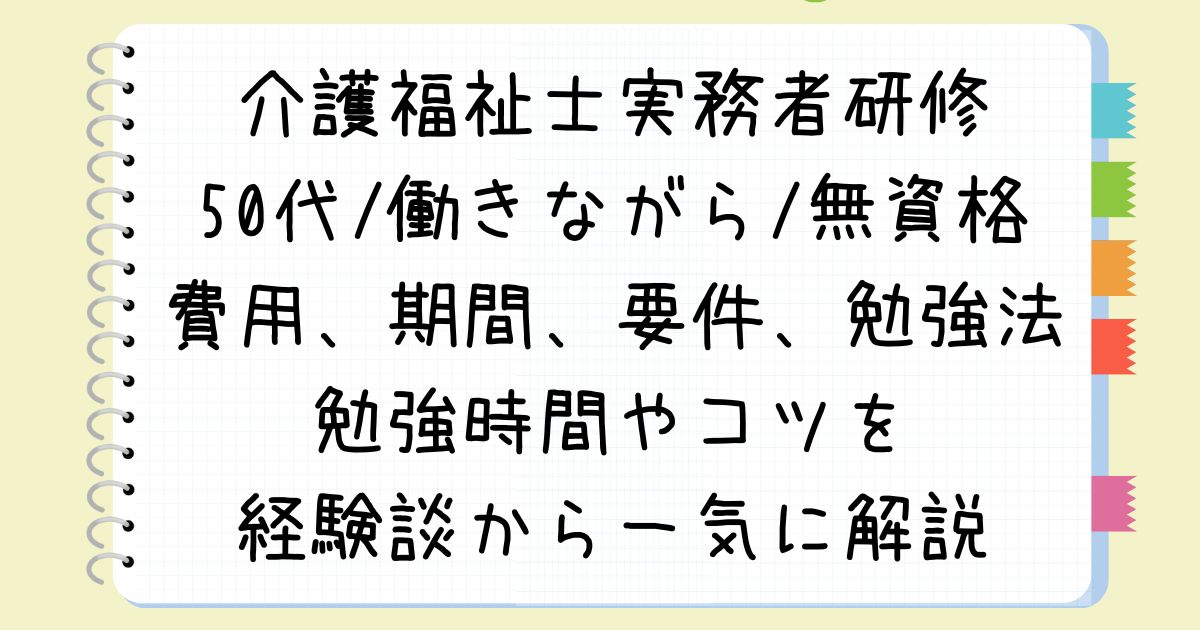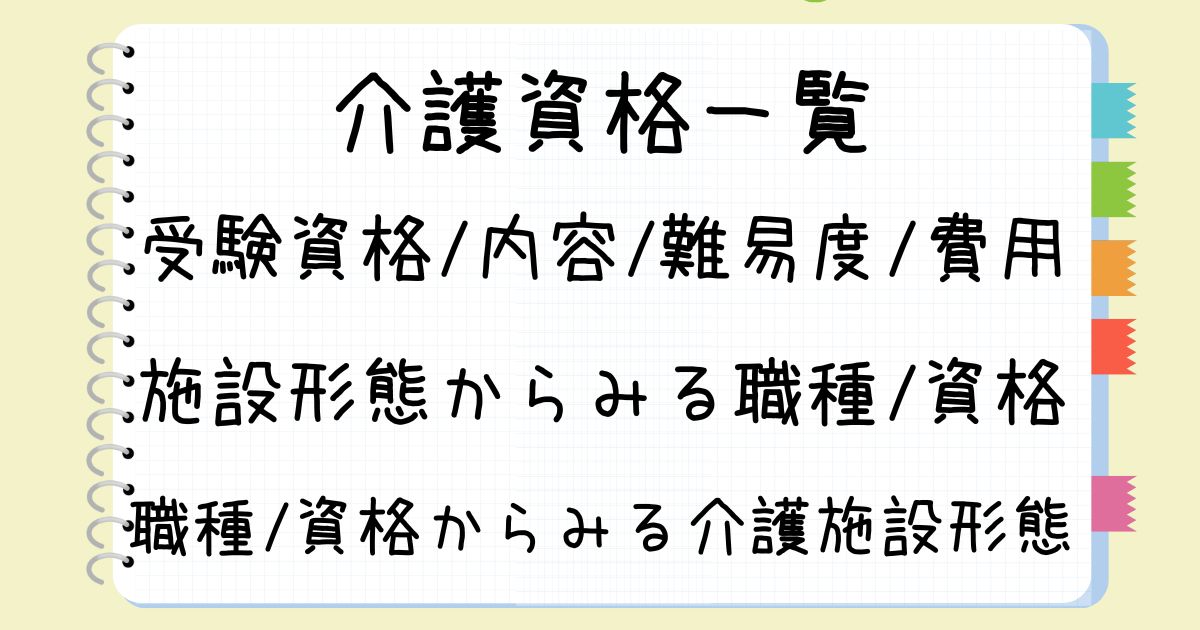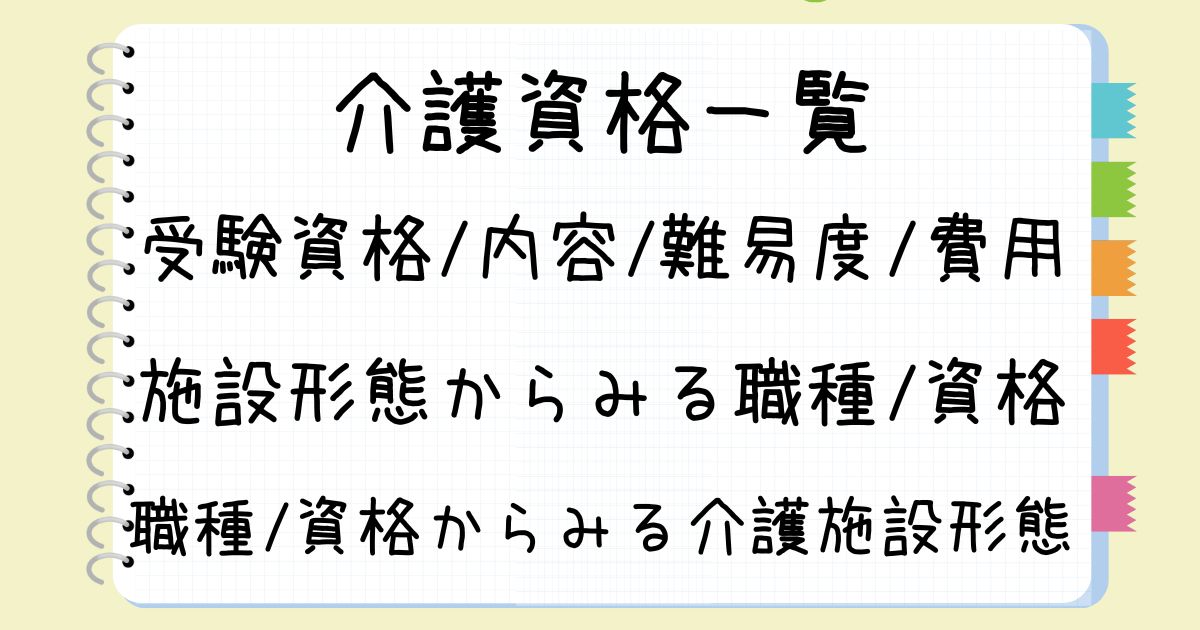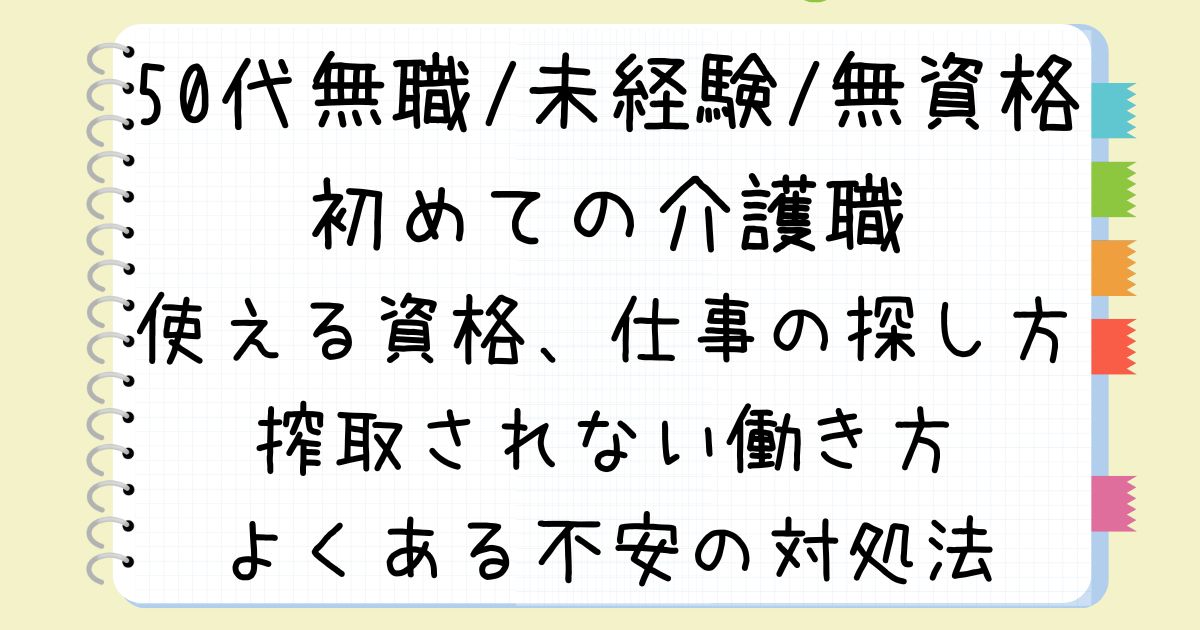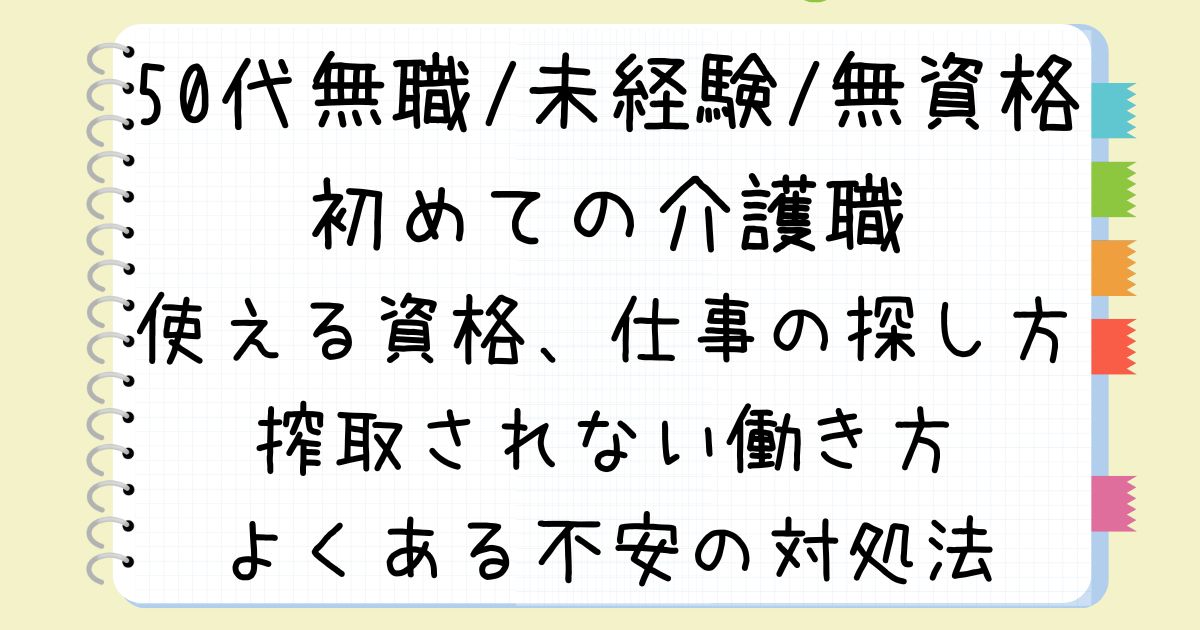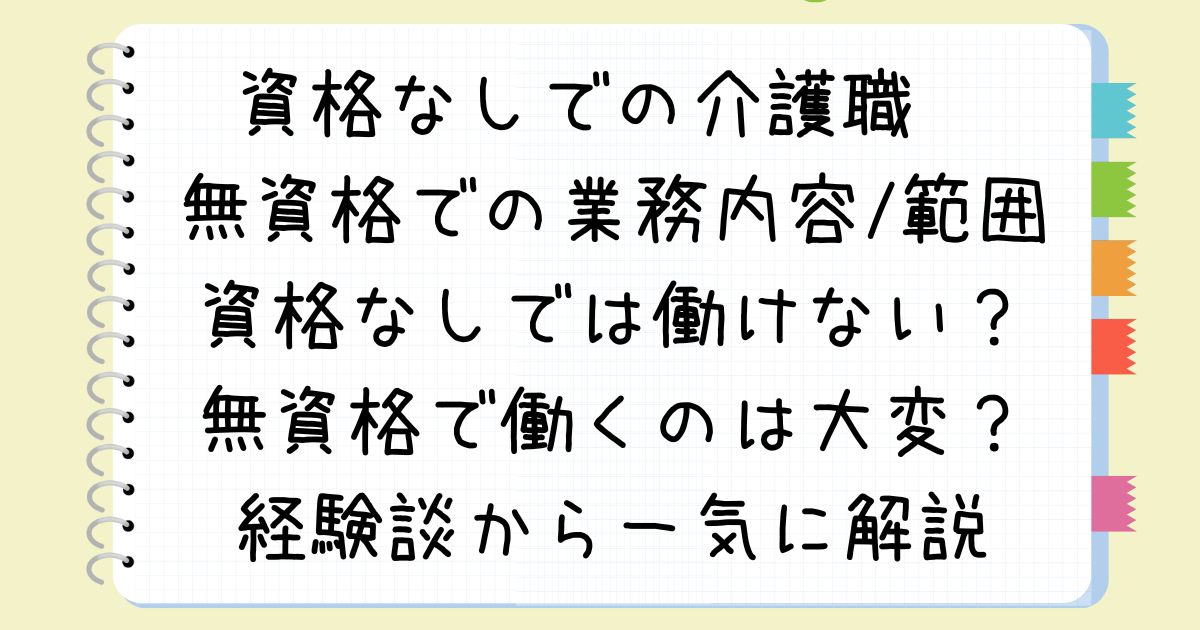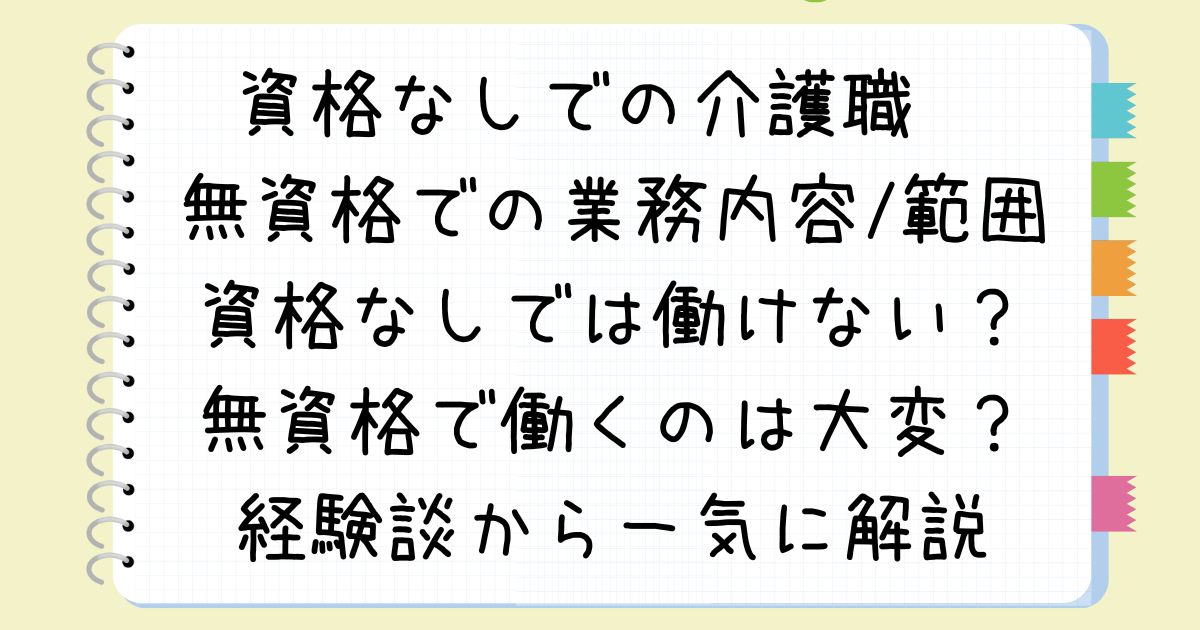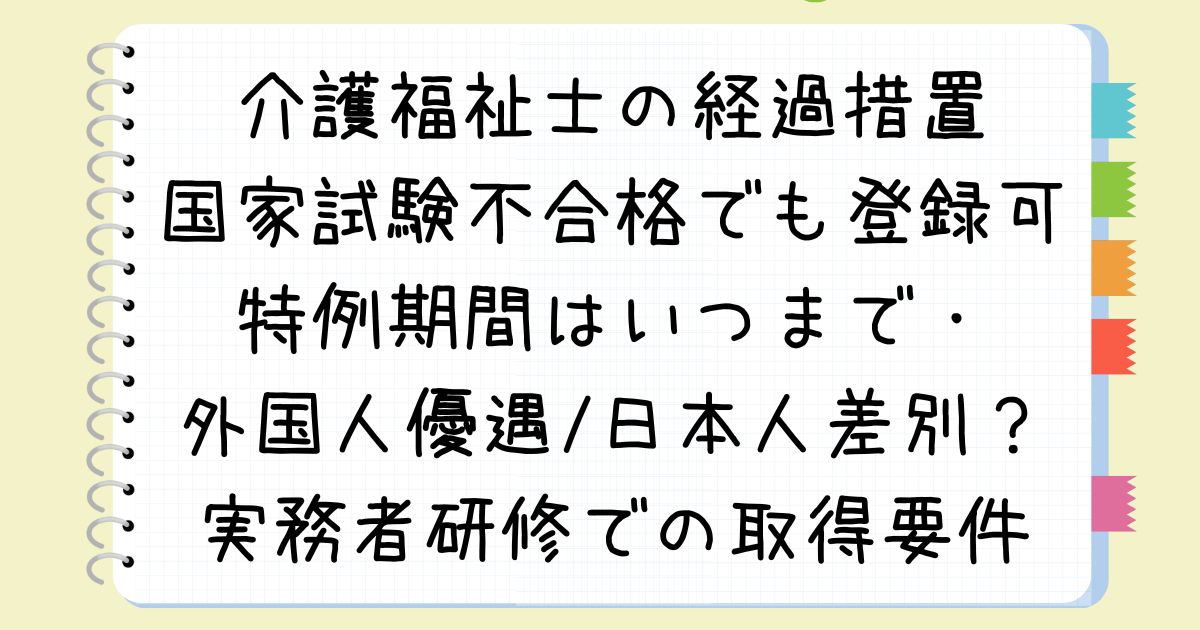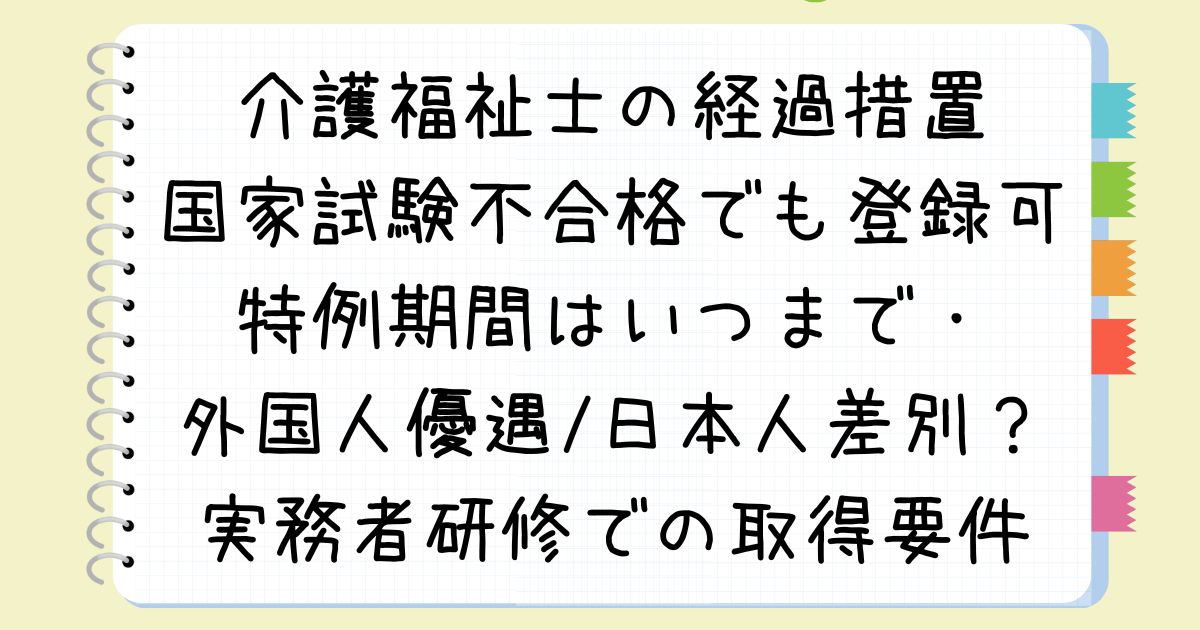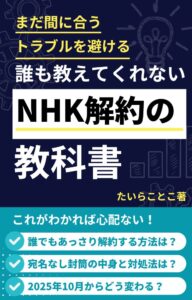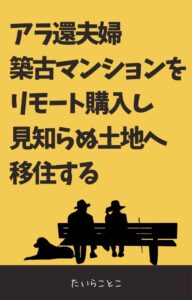実務者研修「介護過程Ⅲ」スクーリングの講義内容、テスト内容、難易度、不合格はあるのか、合格のコツを受講者が解説
介護福祉士実務者研修での「介護過程Ⅲ」スクーリングの内容や難易度等をまとめておきます。
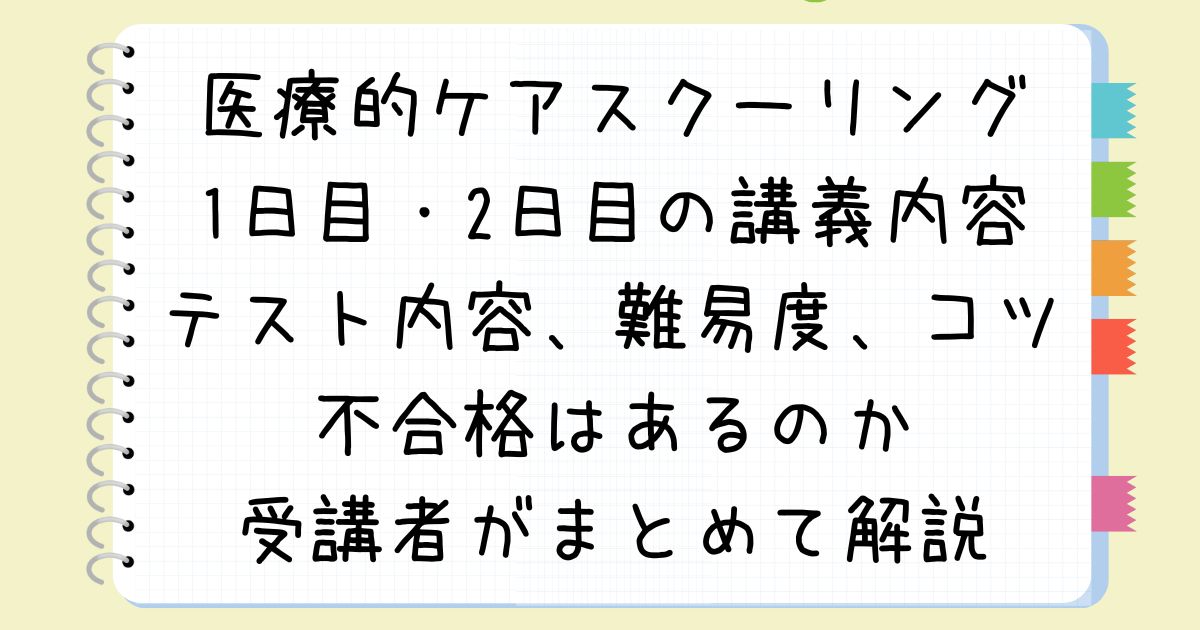
介護課程Ⅲ スクーリングでは何をするの
介護福祉士実務者研修の「介護過程Ⅲ」のスクーリングでは、次の内容の演習があります。
【実務者研修 介護過程Ⅲ 演習内容】
- 介護過程の意義と目的:アセスメントの書き方
- 介護過程の事例展開:アセスメントから介護計画を考える
- 移動・衣類・排泄の着脱の意義と目的:介護計画をもとに演習
- 記録の書き方・情報共有・介護過程の展開のまとめ
与えられた事例をもとに、個人での作業やグループディスカッションを通じて、介護過程の展開を実践的に学びます。

難しくてキツイ…
というレベルではありませんが、
「とりあえず座ってれば誰でも取れる」というほど、安易なものでもありません。
介護過程Ⅲ スクーリング 1日目〜5日目の流れと内容
講義は、基本的に終日。私の受講したところでは、90分4コマ+45分が1コマで1日分。
スクーリングでの受講時間数には規定がありますが、スクールによって、日数や受講時間数が異なります。5日間の通学で済むこともありますが、スクールや地域によっては7〜10日程度の通学が必要なこともあります。
なお遅刻は厳禁。遅刻すると、出席扱いにならず、再受講や振替が必要になります。



10分以内の遅刻が認められているのは初日だけ。
2日目以降は遅刻は認められない決まりとのこと。
介護過程Ⅲ スクーリング 1日目の内容〜アセスメント
ICF(国際生活機能分類)の視点をもとに、利用者(サンプル)の基本情報を整理し、生活全体像を捉え、情報整理シート/アセスメントシートの書き方を学びます。
事例を読み込み、その人はどんな人で、どのように暮らし、本人や家族が何を望んでいるのか、課題はなにか、といったことを、事例の本人プロフィールや標準項目の確認内容、サービス計画書(ケアプラン)から情報収集し、整理していきます。
あくまで事前評価。
利用者情報を把握し、情報共有できるよう、必要な情報をどうまとめるかの練習です。介護の方法論を考えるわけではありません。
個別に情報整理シート/アセスメントシートを記入し、その後グループディスカッションで記入内容やその根拠などを確認する作業を行いました。



テキストにも、情報整理シート/アセスメントシートの事例が記載してあるはずです。
事前に読み込み、どのようなことを、どのように記入するのかなどのポイントを押さえておくと、さほど難しくありません。
ただ、実際限られた時間内で、手書きでシートを埋めるのは、結構大変というか面倒な作業だな、というのが率直な感想です。
介護過程Ⅲ スクーリング 2日目の内容〜介護計画
1日目のアセスメントで得られた情報をもとに、介護計画をたてます。
- 事例の利用者2名それぞれのアセスメントで洗い出した情報の分析
- 分析した情報を統合化し、今後の予測をたてる
- どのような課題や必要性があるのかを検討
- 短期目標をたてる
- 短期目標達成のための具体的な援助内容や方法を検討
といったことを、行います。
介護過程の展開において、アセスメントで得られた20も30もある細かな情報を、移動/移乗・排泄・着替えなどの課題ごとにグループわけし、簡単にまとめて(分析)、今後の”前向き”な予測をたてます。
”前向き”な予測とは、「利用者が、○○することで○○できるようになる可能性がある」という考え方。このままだと「○○できなくなる/しなくなる可能性」というのがマイナス方向の予測になります。



利用者(事例)が今抱えている課題に対して、どういう支援をしたら、よりよい生活につながる可能性があるのか、を想像します。
正解は1つではないので、大丈夫。
この際、介護職員が提供するサービスと、医者や看護師、PTなどが提供するサービスとは切り離し、介護職としてのサービスの範囲でまとめます。



あくまで、介護職のサービスの範囲内での予測です。
かつ、主語は利用者。
わかりやすく言語化する作業ですから、介護経験というよりも、国語力と想像力が問われます。
その予測をもとに、事例の人の生活上解決したい課題/必要性を考え、その課題/必要性を解決するための短期目標を立てます。
排泄・移乗/移動、着替え、食事などの1つの課題に対して、基本的に短期目標も1つ。
現状の改善、悪化予防、現状維持のための課題を解決するための、具体的で、利用者も理解・納得し、関係者で共有できる目標とします。



あくまでベースはケアプラン。
自分でゼロから目標を考えるわけではないので、さほど難しくありません。
この短期目標も、主語は利用者です。
そして、短期目標を達成するための、介護者ができる具体的な援助内容や方法を考えます。
援助内容や方法は、1つではありません。挨拶、体調確認、同意、励ます、褒める、見守りなども含みます。
ここは、介護経験のある方の方があっさり思いつきそうですが、ど素人でも想像力でなんとかなります。



課題をクリアするために、介護者は、利用者に対して、どのような支援ができるのか・必要とされるのかを想像すると、それなりに書けるものです。
テキストにも、援助計画の展開例が複数記載してあります。それを読んでおけば、どのように・どの程度の量でまとめ、具体的に言語化していくかわかります。
いずれも、個別に分析や予測、課題、目標などを検討し、その後グループディスカッション。他の人の考え方や視点にも触れながら、介護計画の立て方を学びます。



情報分析・統合化・予測・目標設定・具体的な援助内容や方法…
というと、果てしなく大変そうですが、全過程をゼロから作り込むわけではありません。
考え方や書き方を学ぶための演習ですし、ある程度は用意された資料にも記載されているので、なんとかなります。
むしろ、グループディスカッションで施設勤務の方の考え方や視点などを知ることができるので、いい経験と学びになりました。
*ディスカッションとは言いますが、そんなに深いものではありません。順番に発表し、違う意見や視点があれば言うこともある、という程度。
介護過程Ⅲ スクーリング 3日目の内容〜移動・更衣介助
2日目で立てた介護計画をもとに移動や更衣介助の演習をします。
必要な用具の配置、その意図、利用者の健康状態の観察、説明・同意、介助、利用者の観察をする視点など、それぞれ具体的に考えていきます。
まずは個人で考え、グループディスカッション。そして、ロールプレイングで演習を行います。



言語化された短期目標には、個人差がありますが、同じ課題に対して目指すところは同じ。
演習は、短期目標をクリアするために、、というよりも、このシチュエーションなら、どこに何をどのように置くのか、介護者の立ち位置、安全確認、体調確認、かけるべき言葉や配慮、注意点などを、ロープレを通して確認していきます。
受講者の日頃の癖というか、仕事ぶりが垣間見られて、学ぶところが多いです。
介護過程Ⅲ スクーリング 4日目の内容〜移動・排泄介助
2日目で立てた介護計画をもとに、車椅子への移乗、車椅子での移動、排泄介助(おむつ交換)の演習をします。
必要な用具の配置、その意図、利用者の健康状態の観察、説明・同意、介助、利用者の観察をする視点など、それぞれ具体的に考えていきます。
中心となるのは、利用者とのコミュニケーション、安全確認、状況に応じた介護者の立ち位置、必要な配慮など。細かな手技の確認や指導はありません。そこは、介護職員初任者研修で習得するものとされているからです。
おむつ交換では、受講生同士で介護者・利用者の役をします。利用者役をする時には、自分が来ている服の上からオムツをし、その上にパジャマを着せてもらいます。



前開きのパジャマの用意が必要になっているかと思いますが、普段のサイズより1〜2サイズ大きめ、女性なら男性用のパジャマでもいいくらいです。
介護過程Ⅲ スクーリング 5日目の内容
最終日は、モニタリングについて学びます。
介護計画でたてた短期目標を達成できているのかを確認するための、観察の視点を具体的に検討します。



職場では月末に常勤スタッフが、モニタリングをしています。
大変そうですが、何をしているのかよくわからない、というのが正直なところ。
モニタリングや、短期目標の評価など、お気楽パートでは知らない介護過程に触れる貴重な機会でした。
その後、自宅学習の確認として、20問程度の○×式の簡単なミニテストと、3日目に行った移動介助を講師を利用者役として実演。
3日目の演習で学んだことを、講師相手に再度確認。試験というほど厳格なものでもありませんが、「学習到達確認」として、修了判定の判断の1つとされます。



20人程度が1人ずつ行いますので、なんだかんだと2時間くらい。
最終日の午後のほとんどがコレ。
講師を相手に1人ずつの実演というと緊張しそうですが、3日目でグループワークやロープレ演習で行ったことの復習です。新しい課題ではありません。



かなり緊張された受講生もいましたが、私は最終日だったので、ダラダラモード全開。待ち時間にイメトレで復習し、多少のミスはあったもののなんとなく終了。
実演がそこそこの形になっていれば、講義内容を理解しているということで「学習到達」したことになるので大丈夫。
介護過程Ⅲ スクーリングでのテスト/試験・学習到達確認
私が通ったスクールでは、スクーリングでの”筆記試験”はありませんでしたが、「学習到達確認」というものがありました。
学習到達確認① ミニテスト
在宅学習の「確認」という形で簡単なミニテストのようなものがありました。
○×形式20問程度、合格ラインがあるわけでもありませんし、ほとんどの問いは介護界隈の一般知識でも解けるレベルの内容です。



満点でなければ気がすまない完璧主義であれば、テキストを再度通読するといいですね。
修了できれば別に構わないけど、、という方は、改めて復習などしなくても、、、という感じ。
スクールによっても違うでしょうし、介護福祉士の国家試験を受験予定であれば、テキストを復習しても損はないので、復習するほうがいいかとは思います。
学習到達確認② 介助の実演確認
最終日の講義内容でも触れましたが、講師が利用者役となって移動介助の確認を行います。
1人ずつの実演確認ですから、2時間程度かかります。その間、テキストや資料の確認、おしゃべりは禁止。
あくまでも「学習内容の理解を確認」するのが目的らしく、実演時に抜け・モレ・間違い等があれば、自分の持ち時間内に自己申告も可能。採点基準がどのようなものかは分かりませんが、かなりユルイとは思います。



そもそもで、合否判定するための試験ではありません。
「講習で学んだことは理解してます」というのが確認できれば大丈夫、、という感じ。
学習到達確認③ 平常点
「学習到達確認」ではありますが、受講中の態度、資料作成、グループワーク、ロープレなどの平常点も加味されるとのこと。
遅刻しない・授業中寝ない・作成する資料はきちんと書く・グループワークやロープレに参加する、のようにオトナとして普通に受講すれば問題ないでしょう。



全部合わせての「学習到達確認」になるようです。
介護過程Ⅲ スクーリングの難易度
ド素人がいうのもなんですが、正直スクーリングの難易度はさほど高くありません。
スクーリングでの不合格者はでるのか
講師曰く、時折不合格者が出るようです。
ただ、「座っていれば修了というものではなく、ちゃんと勉強はしてね」という感じです。
私が受講したクラスでは、不合格者はいませんでした。
スクーリングで軽く合格するには
1日目のアセスメントや2日目の介護計画は、テキストの介護Ⅲの箇所を読んでおけば問題ありません。
当日に、講師の説明もありますし、実際に自分で書いて、その後のグループディスカッションで他の人の考え方を聞く機会もあります。正誤のテストとは異なりますでの、構えて臨むほどのものでもありません。
3・4日目は、介護計画をもとに移動・更衣・排泄介助の演習があります。
とはいえ、細かな手技の確認ではなく、利用者とのコミュニケーション、安全確認、体調確認、短期目標を達成するために必要とされる具体的な援助、注意点などを考えるのが中心です。
YouTubeなどの動画を見たり、市販されている介護の本を読んでおくと安心ですが、事例の情報やケアプラン、アセスメントなどから、どんな介助/援助が必要なのか、どんな危険性があるのかなどを、想像してみることのほうが重要です。
手技に関して不安があれば、どの程度の予習が必要かを演習日前に講師に確認することをお勧めします。



私が受講したクラスでは、介助Ⅰ・Ⅱの該当箇所を読んでおくことと、スクーリング1・2日目の復習の方が大事と言われました。お言葉に甘えて、テキストの復習程度で参加しました。
なんとかなるものです。
↓介護術の画像と解説が見開きで、わかりやすくまとまっています。Kindle Unlimited対象。無料で読めます。
実務者研修を受けている人ってどんな人?
職場の先輩から、初心者講習や介護職経験なしに、最初から実務者研修を受ける人もいるけど、少ないという話は聞いていましたが、実際本当に少ない。
私が参加した「介護Ⅲ」と「医療的ケア」のスクーリングには、同時期の受講生が合わせて40名程度いましたが、みなさん経験者。しかも、ベテランクラスの介護職の方が多かったです。
短い方でも2〜3年、10年越えの方も複数。
年明け、もしくは来年度の介護福祉士を受験予定されている方もいました。
私が受講したクラスでは、グループホームやサ高住、特養・老健・病院などの施設勤務、訪問での身体介護などで働いている人がほとんどでした。デイサービスやデイケアなどの通所の人は、ほんの数人。
受講全体を通して、経験の差を見せつけられたのは、介護Ⅲ スクーリングでの3日目・4日目。特に4日目。
私は、通所施設で週2日勤務していますが、排泄介助でリハパンの履き替えはあっても、オムツ交換をする機会はありません。おむつ交換は、スクーリングが私にとってのデビュー戦。
一人だけド素人なので変な緊張感と恥ずかしさはありますが、所詮研修。開き直って参加しました。
むしろ、他の受講者の手技を見ることができたことで、学びも多く、いい経験になりました。
スクーリングを受ける順番
実務者研修の通信教育やオンライン受講には、「介護過程Ⅲ」と「医療的ケア」の2種類のスクーリングがあります。
スクーリングを受ける順に指定があるかは、スクールによります。
- どちらを先に受講してもよい
- 介護過程Ⅲ → 医療的ケア
の、いずれかです。医療的ケアを先に受けるよう指定しているスクールはないかと思います。
指定がない場合には、どちらを先に受講しても問題ないと思います。
内容がかぶるわけではないので、スクーリングの演習時に困ることもありません。
ただ、スクーリングに参加する前に必要な課題提出などのスケジュールが変わってきます。申込時によく確認する必要はあります。