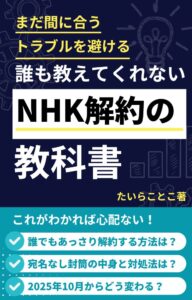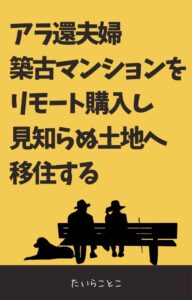学校や習い事の生徒の家族の葬儀〜参列、通夜か告別式か、香典相場、参列しない場合の対応
生徒の親や親族が亡くなった場合、お葬式(通夜/葬儀/告別式)への参列や香典、供物などについて、基本的な考え方をまとめておきます。
職種、生徒との関係、地域性などによっても異なりますので、唯一の正解などはありません。自分の中でルールを決めておくことが大事です。
生徒や生徒親族のお葬式への参列
「生徒」といっても、生徒との関係性によって、対応が異なりす。
学校の生徒の場合
学校関係では、児童・生徒もしくは、その保護者が亡くなった場合の対応は、慶弔規定が明確に定められています。
学校や地域によって異なりますので、慶弔規定を確認する必要があります。
故人やご遺族に特別な思い入れがあったとしても、他の児童・生徒と対応に差が出ないように、配慮が必要です。
塾や習い事などの生徒の場合
習い事の場合には、個人で教えているのか、組織の中で教えているのかによっても異なります。
個人で教えている生徒の場合
個人事業主等で個人的に教えている場合には、明確な決まり事はありません。
自分の中で決めておくといいでしょう。例えば:
- 生徒本人が亡くなった場合には参列
- 生徒本人及び1親等(親や子)が亡くなった場合には参列
- ◯年以上のお付き合いがある場合には参列
- 参列はせず、香典だけ渡す
- 参列・香典はなしで、弔電を送る
- 参列・香典・弔電など一切なしで、お悔やみだけ伝える
生徒さん同士が知り合いとなるような場合には、意外と情報が広がるものです。
生徒本人やその親族が亡くなるようなことは、そう頻繁に起こるものではないと言え、「◯◯さんの時には参列したのに、△△さんの場合には何もなかった」など噂が広がる可能性もあります。
不要なトラブルを抱えないように、明確にしておくといいでしょう。

私も、過去に個人レッスンで教えていたことがありますが、生徒さんの親族の葬儀には参列したことがありません。お悔やみを伝えただけで、香典や弔電、供物などもしませんでした。
生徒さんから受けた訃報も、「亡くなったのでレッスンを休む」といったもので、葬儀の詳細などの連絡はありませんでした。
組織下で教えている生徒の場合
◯◯教室など、企業で運営している塾や習い事であれば、運営側で慶弔規定があるはずです。個人で判断せず、運営側に報告し対応を確認する必要があります。
運営側に慶弔規定がない場合もありますが、その場合でも、相談して決めるといいでしょう。
生徒の親族の範囲
習い事などでは、「生徒の親族」は、基本的に1親等までで考えます。
つまり、生徒本人、生徒の配偶者、生徒の両親、生徒の子。
祖父母、叔父叔母などは含めないことが多いです。
ただ、習い事の送迎が祖父母である、保護者が両親以外、など、事情がある場合には、その都度の判断になるでしょう。
参列するなら通夜か告別式か
慶弔規定がある場合
慶弔規定がある場合には、その規定に則り参列します。
学校であれば、校長先生や担任、もしくはその代理は告別式(葬儀)への参列が認められています。
規定に記された先生以外は、日中に営まれる告別式(葬儀)への参列は難しいため、お通夜へ参列、もしくはお通夜の後での弔問に伺うことになるでしょう。
学校や地域によっては、学校の代表が参列するため、他の教師や職員の参列や弔問はしないこともあります。
慶弔規定がない・該当しない場合
慶弔規定がない場合や、規定に記された範囲に該当しない場合には、それぞれの判断となります。
本来であれば、葬儀・告別式への参列が望ましいのですが、仕事や授業などの都合で難しい場合には、お通夜への参列、もしくは通夜後の弔問に伺うことになるでしょう。
これは「生徒」及び「生徒の親族」に限らず、会社の社員やその親族、取引先の社員やその親族でも同様です。
昔は、お通夜というのは親族などの身内が中心で、一般の人は告別式に参列するものでした。
現在は、社会生活や考え方の変化もあり、お通夜にも一般の方が参列します。仕事の都合などで、告別式に参列できないため、お通夜のみの参列ということも珍しくありません。もちろん、故人やご遺族と親しくお付き合いのある方は、お通夜と告別式の両方に参列することもあります。
お通夜の服装は喪服なのか
お通夜での服装は、本来喪服ではありません。男性であればダークスーツに黒のネクタイ、女性であれば暗い色合いのスーツやワンピースが基本です。
仕事帰りにそのまま弔問に伺う場合には、アクセサリーなど華やかなものを外す程度でも構わないのです。
ただ、近年お通夜でも喪服で参列される方が増えているようです。地域性もありますので、服装は周りの方に確認する方がいいでしょう。
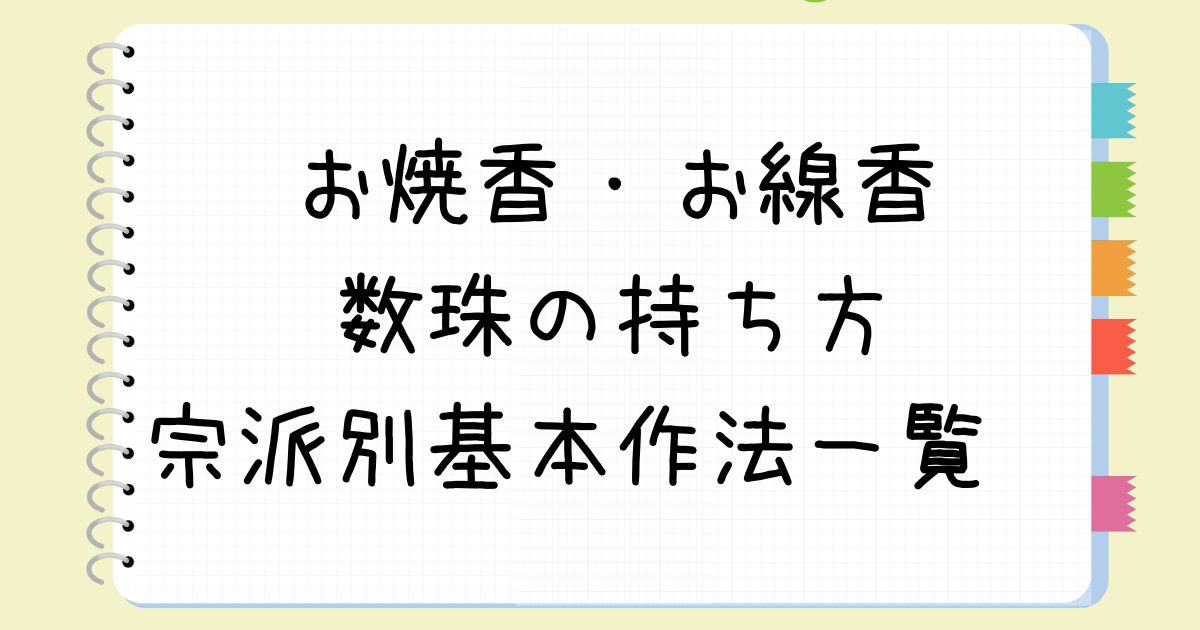
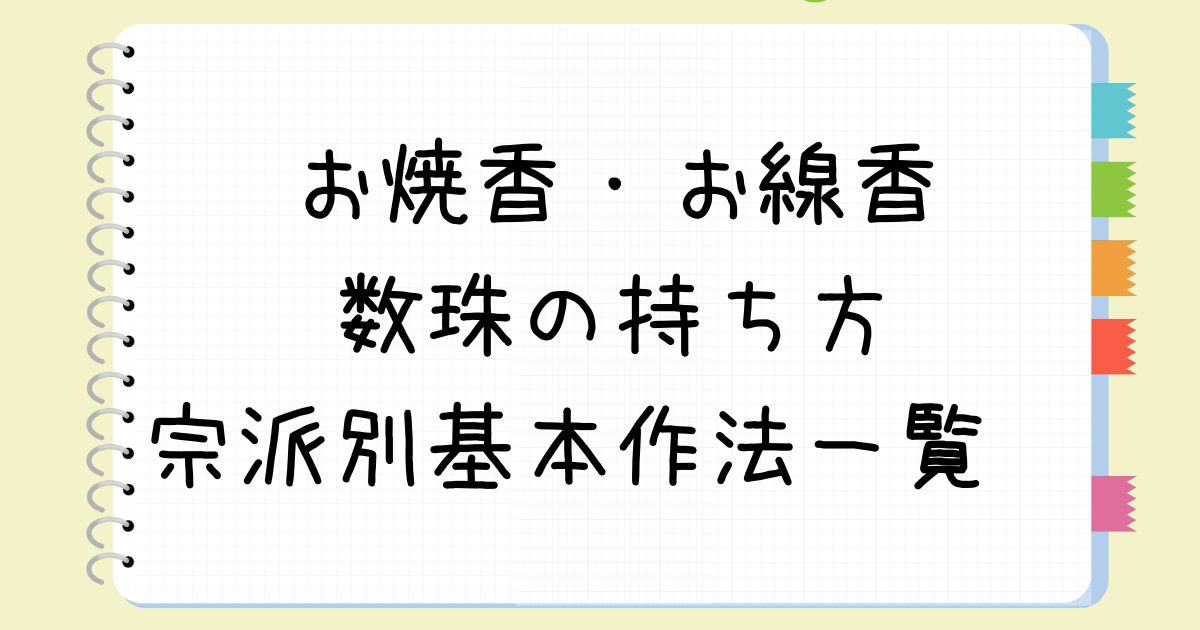
生徒や生徒親族への香典相場
慶弔規定がある場合
慶弔規定がある場合には、その規定に従います。
学校や職場の代表として参列する場合には、PTAから「弔慰金」として支給されるものを「香典」という形で持参することもあります。
また、学校から一部支給され、そこに個人で上乗せすることもあります。
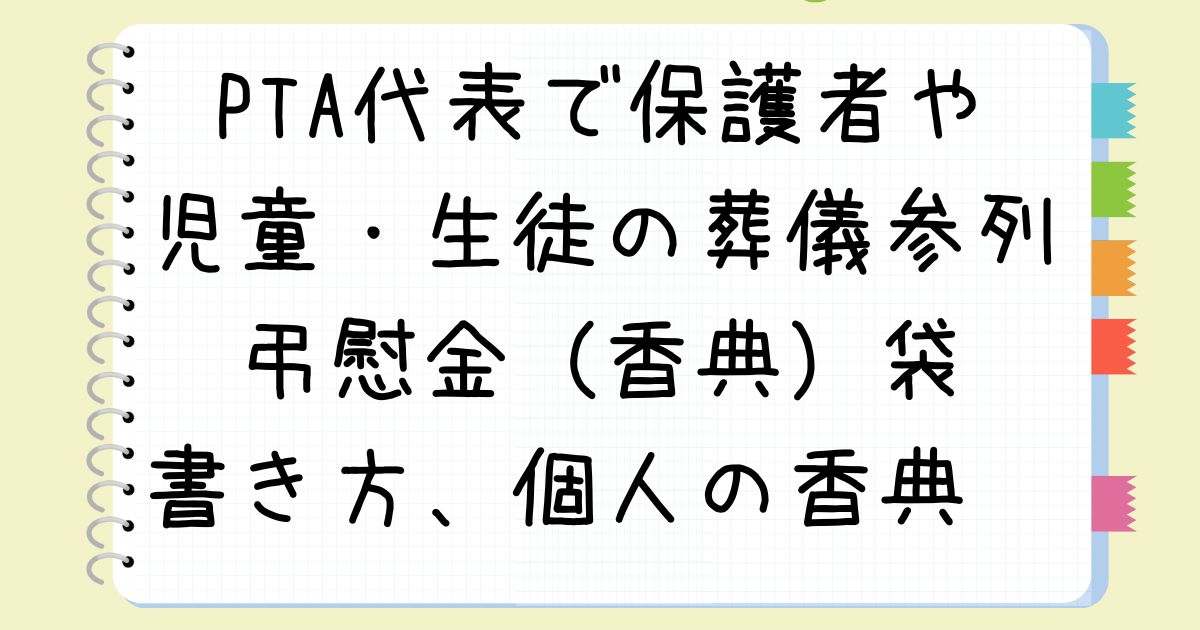
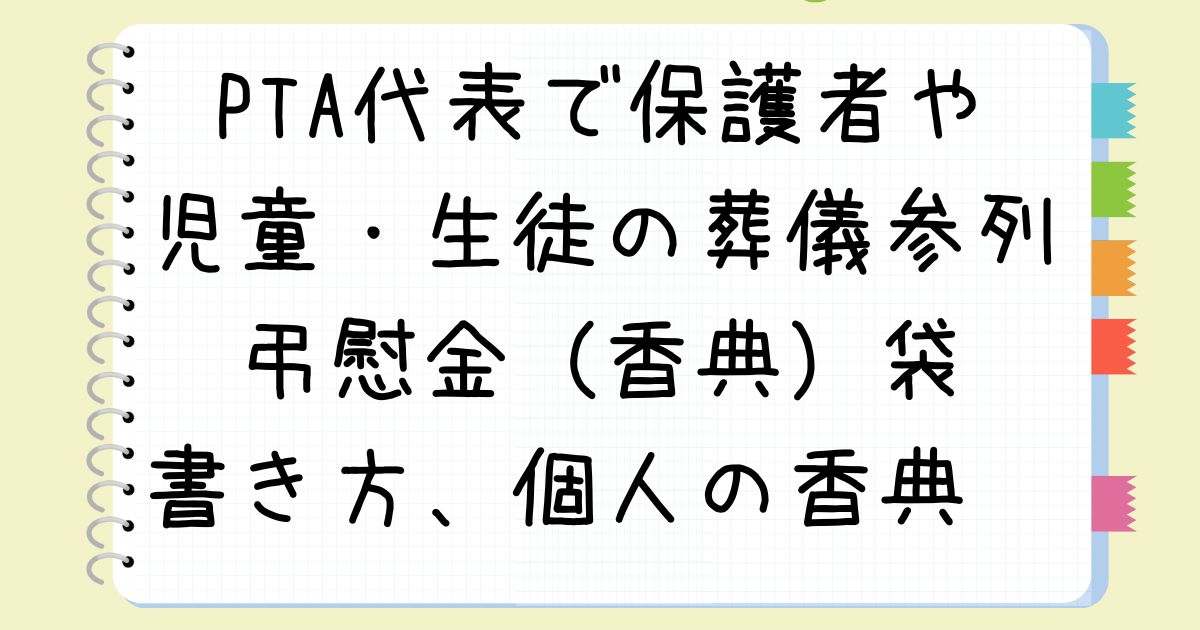
慶弔規定がない・該当しない場合
【香典相場】
- 生徒本人:3,000円〜10,000円
- 生徒の配偶者、親や子:5,000円
香典には、地域的な相場や年齢的な相場、故人との関係性による相場などもありますが、生徒の親であれば、5,000円程度が無難なところでしょう。双方にとって、多過ぎず、少な過ぎずのところです。
故人が生徒本人の場合には、故人の年齢、お付き合いの長さなどによって判断することになりますが、こちらも5,000円程度が無難なところでしょう。
故人によって香典の金額を変える方が問題になることもあります。さすがに、「香典が◯◯円だった」など、噂が広まることはないでしょうが、こちらには1万円、あちらには5千円というように、差があるのはいいことではありません。
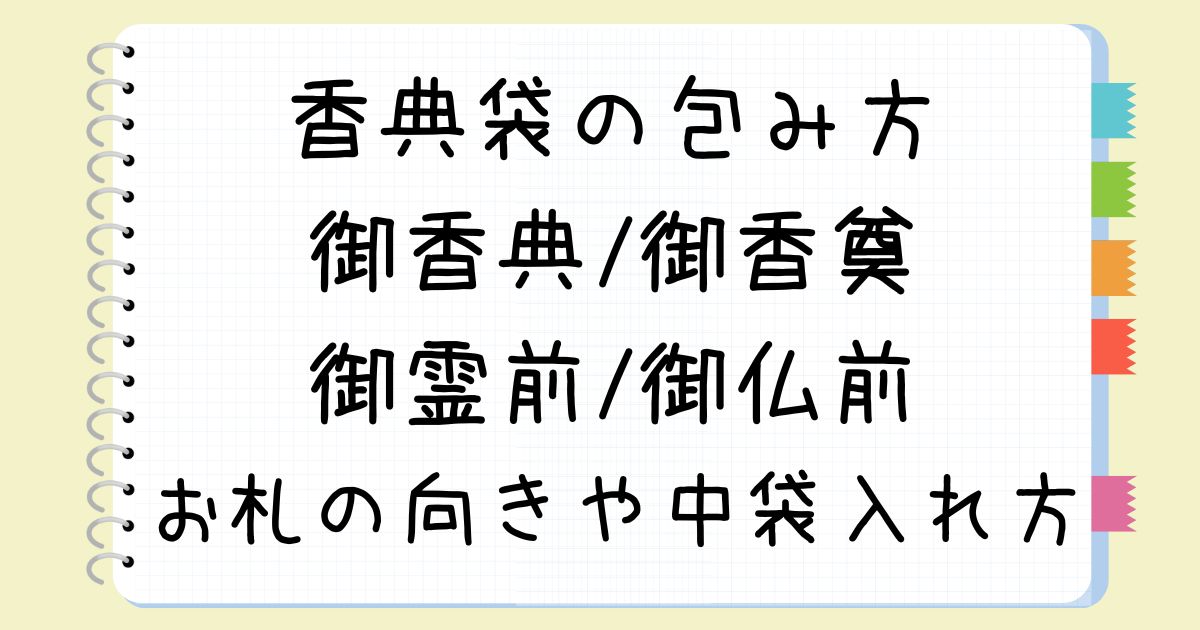
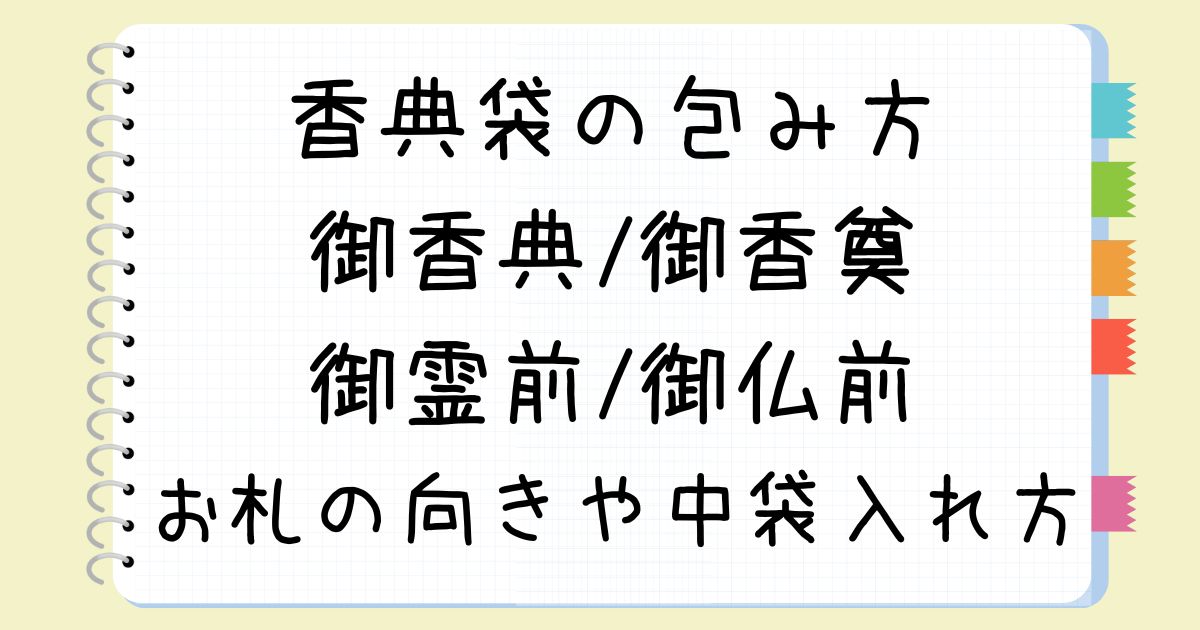
記帳、香典や弔電・供物などの住所
お葬式(通夜/葬儀/告別式)受付での記帳、香典を包むにしても、弔電や供物を送るにしても、住所や氏名を記入する必要があります。
氏名はともかく、自宅住所を記入することに躊躇する場合もあるかもしれません。
本来は、自宅住所を記すものですが、知られたくないといった事情がある場合には、塾や習い事などの教室の住所を記入することもできます。公民館やレンタルスペースを借りて行なっている場合には、難しいですが…
生徒や生徒親族の葬儀に参列しない場合の対応
生徒やその親族へのお葬式(通夜/葬儀/告別式)に参列しない場合の対応も、自分の中で決めておくことをおすすめします。
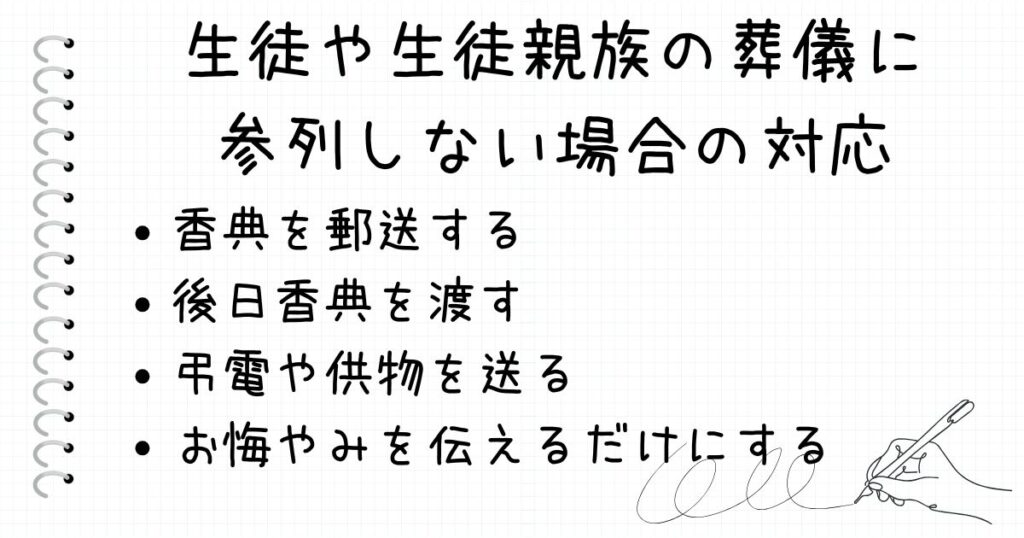
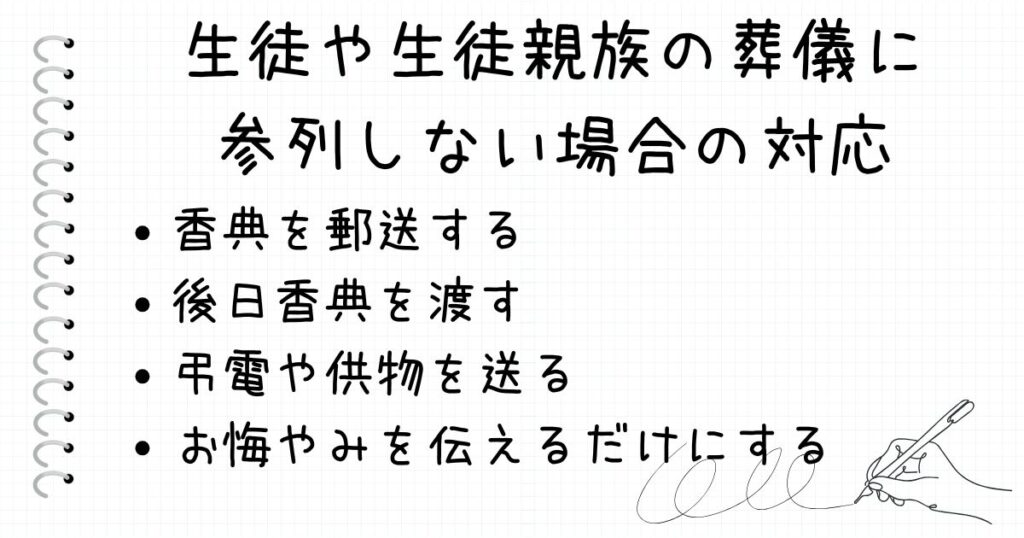
香典を郵送する場合には、現金書留を使います。
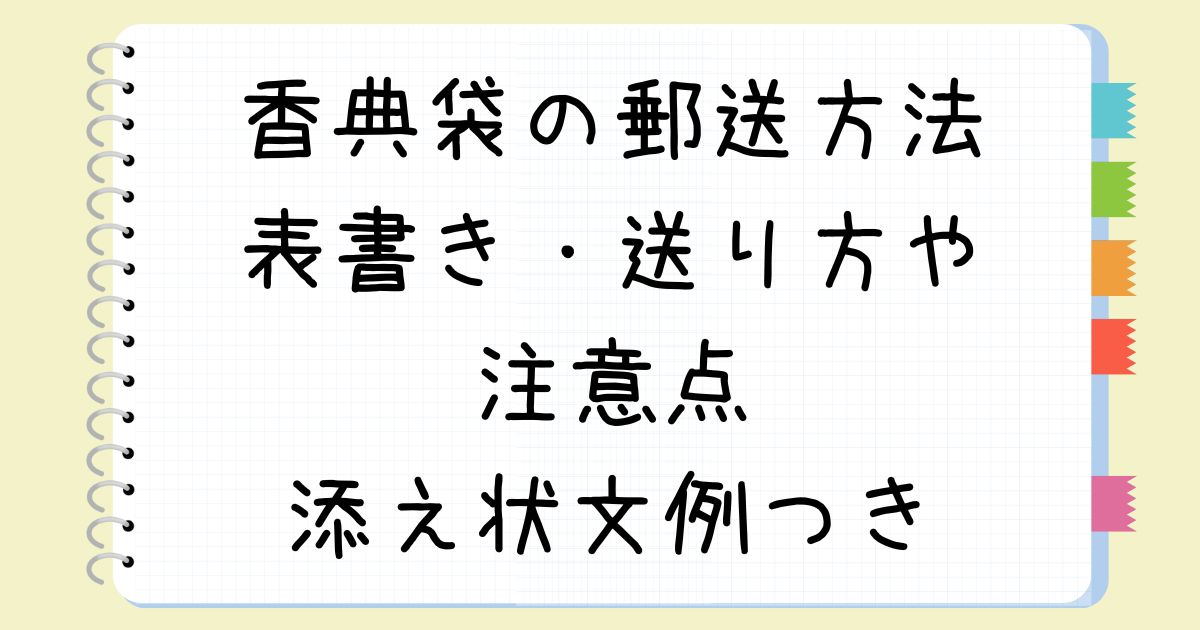
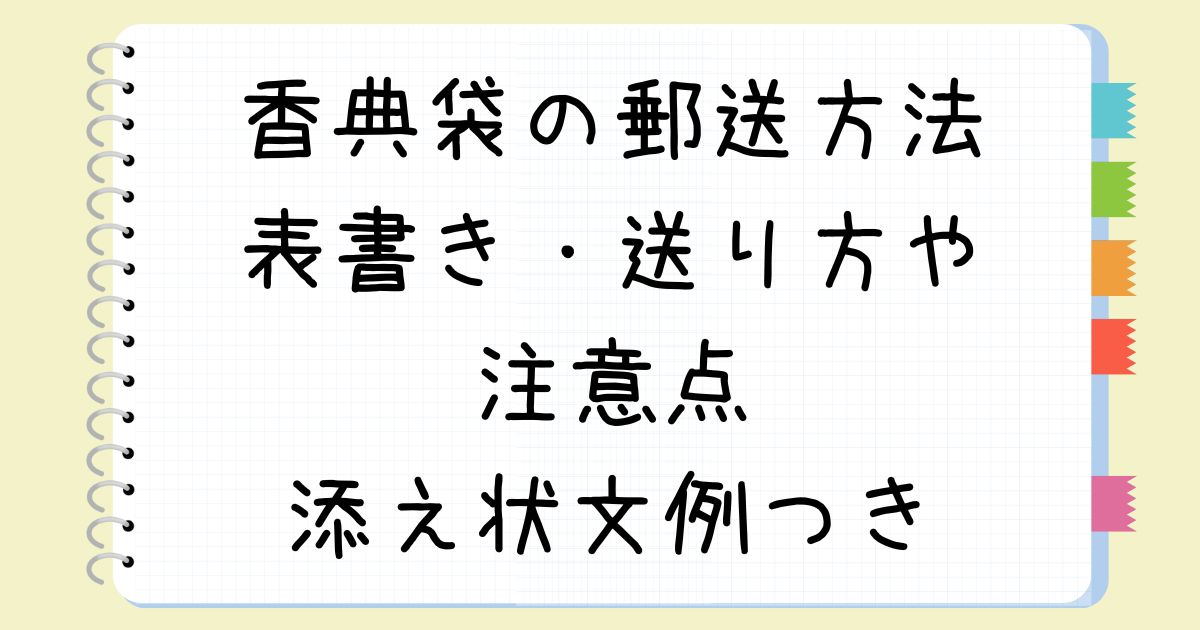
弔電や供物であれば、ネットで手配できるので簡単です。
何かできることをしたいと思っても、何もせず、お悔やみを伝えるだけでも構わないでしょう。



生徒やそのご家族と、長いお付き合いがある、直接知っているような場合でなければ、葬儀日程や場所などの詳細を知ることさえないかもしれません。習い事の種類にもよりますが、、
情報の入り方によっても、できる対応も限られてきます。