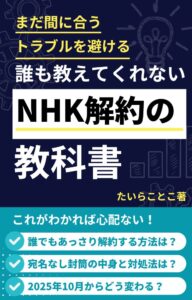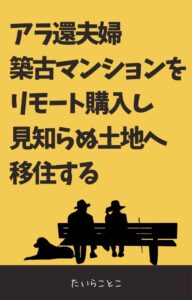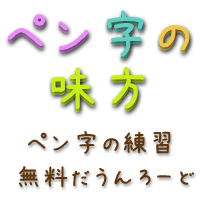字が汚くてストレスを感じたら〜50代でも自力で汚文字・クセ字を直すオススメの方法、経験談
デジタル化で文字を書く機会が激減。
書類の提出などで必要に迫られペンをとると、自ら書いた文字のあまりの下手さ、汚文字ぶりにには、恐怖に近い不快感さえ感じます。
自分用のちょっとしたメモ程度ならともかく、提出書類など他者がそのキタナイモノを読まなけらばならないのかと思うと、ひたすら申し訳なく、恥ずかしく思えるほど。
でも、大丈夫です。
オトナになってからでも、50代のオバサンになってからでも、自力でなんとかすることはできます。多少の手間はかかりますが、時間もお金もかけずにできる方法をまとめておきます。
字が汚くなったとストレスを感じるワケ
もともと字を書くのが上手ではないと感じている人は、自分の書く文字が嫌いだったり、人に見られることに抵抗を感じたりしがちです。
そこに、「前よりも字を書くのが下手になった」「字が汚くなった」と気がついてしまうと、かなりのストレスを感じますが、これには理由があります。
自己評価の低下
今の子ども達はわかりませんが、昭和生まれは、子どもの頃から「心を込め」「きれい」で「丁寧な」字を書くことを教えられ、良くも悪くもそれが「良いこと」であるという価値観を植え付けられています。
そのため、字が汚いと「頭が悪い」「性格が歪んでいる」「心が汚い」「丁寧さに欠ける」といった印象を持つ人も少なくはありません。
もともと、自分の書く文字がどれほど上手だったかは別として、自分の字が下手になる、汚くなると「自分の能力が衰えた」「字もきちんと書けなくなった」のように、自己評価が下がりストレスを感じるようになります。
コミュニケーションにおける不安
デジタル化が進む現代でも、手書きの文字は「気持ちを伝える」手段として一定の評価があります。
そのため、字が汚い・上手に書くことができないと、相手に対して失礼、気持ちが伝わらない、読みにくいことで不快な思いをさせてしまうのではないか、雑な印象を与えるのではないか…など、不安を感じることがあります。
特に、手紙やメッセージなどを手書きする際に、このストレスが強くなります。
理想と現実のギャップ
過去に自分が書いた「きれいな字」の記憶と、現在の自分の字との間にギャップがあると、それがストレスの原因になります。
「以前はもっときれいに書けたのに」という思いが、手の震えや筋力の低下などの加齢による身体的な変化やその不安と結びつき、より強いストレスを感じることもあります。

私は、もともと癖のある字を書いていたので、きれいできちんとした字を書けないことを気にはしていませんでした。実際、仕事や生活に支障もありませんでしたし、、
ただ、あまりに文字を書かなくなると、指の筋力が落ちるのか、脳の指令系統になんからの支障がでるのか「さすがにこれでは、日本人として情けない…」レベルの字しか書けなくなりました。
ストレスというよりもヤバイ感が、書写を始めたきっかけです。
年を取ると字が下手になるのはちゃんとした理由があった
私が字が下手になったのは習慣の問題なのかと思っていましたが、年をとると字が書けなくなる・下手になる・汚くなるには、身体的な変化と脳の機能の変化という、全くもって正当な理由が存在します。
字が下手になる身体的な変化
視力の低下
老眼などで近くのものが見えにくくなると、自分の書いている文字を正確に認識できなくなります。結果として、文字のバランスが崩れたり、曲がったりするようになります。



私も老眼クラブ。
書きにくさよりも、読みにくさの方が感じやすい気がします。
読みにくいと、文字を大きくしたり、老眼鏡などを使用したりしますが、多少の書きづらさでは老眼鏡の使用を思いつかなかったりします。
はじめて、老眼鏡を使用しながら字を書いたときには、こんなに違うものかと驚いたほどです。当然、老眼鏡使用の方が、まともな字になっています。
筋力の低下
手や指の筋力が弱まることで、ペンを握る力が弱くなったり、細かい動きをコントロールしにくくなります。これにより、筆圧が不安定になったり、文字の形を正確に保つことが難しくなります。



生活には支障がないため気がつきませんが、たまに字を書くと指や前腕がやたら疲れたり、痛くなったりするのも、おそらくコレ。
筋力の低下というよりも、文字を書くときに使う筋肉の使い方を忘れてしまう、という感じでしょうか。
関節の硬化
指の関節が硬くなったり、変形したりすることで、柔軟な動きが妨げられます。スムーズな運筆ができなくなり、一画一画がぎこちなく不自然な字になることがあります。
手の震え
加齢に伴い、意図しない手の震えが起こりやすくなります。
パーキンソン病などの神経疾患が原因の場合もありますが、加齢による生理的な震えも一般的です。ペンを安定して持つことが難しくなり、線がブレたり、字が乱れたりします。
字が下手になる脳機能の変化
運動機能指令の伝達速度の低下
字を書くという行為は、脳が「文字の形」を認識し、それを手や指に伝える複雑なプロセスです。
年をとると、この脳から手への神経伝達速度が遅くなり、思い通りに体を動かすことが難しくなります。



50代くらいだと、そこまで神経伝達速度が遅くなっているとも思えないのですが、文字を書く時の体の使い方を忘れている感は、かなりあります。
認知機能の低下
記憶力や集中力が低下すると、文字の形や書き順を思い出すのに時間がかかったり、集中力が途切れて文字の完成度が落ちることがあります。



文字を書かなくなると、読めても書けない漢字が爆増するのも、認知機能の低下。
インプットされた情報(文字)を脳が認識する機能は比較的保たれているため読むことはできても、文字の形を想起し、手の動きに変換し、文字を書くというアウトプットするプロセスが、スムーズにいかなくなり、書けなくなります。
脳の萎縮
加齢による脳の萎縮は、運動を司る部位にも影響を及ぼし、細かい運動をコントロールする能力を低下させます。
番外編:性格の問題
このように、加齢による身体的な変化や脳機能の変化が複合的に作用することで、以前よりも字が下手になった、汚くなったと感じることが増えます。
それに加えて、私の場合は「せっかち」という性格の問題もあると感じています。
生活上使用している文字の多くを、キーボードやスマホなどで入力しているため、文字を書くよりも入力するペースが圧倒的に速い。そのスピードに慣れてしまうと、画数の多い漢字を書いているのがまどろっこしく感じてしまいます。
書こうとしていることと、その文字を書く歩調がズレてしまうので、字が流れてしまう。結果、極めて読みにくい、時には自分でも判読不能な文字を書いてしまうような気がします。
50代が自力で「汚文字」から脱出する方法
汚文字脱却レベルを決める
汚文字/下手文字脱却=美文字ではありません。
美文字になりたいのか、それとも汚文字から抜け出したいのか、まずは自分の中の合格ラインを決めておきます。
なお私は、、美文字は目指していないのでこのレベル:
- 疲れず書けるようになる
- 読める文字を書く
- 正しく書く:誤字を減らす・迷わず書ける漢字を増やす
上述していますが、字を書く機会が激減したため、私は文字を書くための筋力や運動機能低下が顕著です。文字を書くと、すぐに疲れ、指や腕が痛くなったり、指が攣りそうになることも。「文字を書く」ための筋力や運動機能の強化、リハビリが必要でした。
認知機能低下で漢字を書くというアウトプットに支障があり、さらにせっかちな性格のため、字が流れてしまったり、曖昧になることで、書いた本人でさえ判読に苦労する字を書いてしまいます。
上手ではなくても、まずは読める文字を書く。気が急いてしまう時には、手を止めてひと呼吸さえしています。
字を書くというアウトプットが苦手ゆえに、誤字が爆増傾向。誤字脱字を減らす、漢字を正しく書く、曖昧な漢字は調べる、など基本的なことを怠らないようにするのが、私の目標となりました。
お手本で文字の書き方・ペンの持ち方の基本から復習
まずは、お手本となる本やサイトで、ペンの持ち方、ひらがな・カタカナ・基本の漢字などの書き方を復習します。
ペン字のみであれば、この1冊で十分です。書き込みしてもいいし、裏紙などに練習してもいいです。とにかく、よく見て、お手本と同じように書くのが、なによりも大切で、最速です。



たくさんの例文や、使う漢字全てのお手本が必要なわけではありません。まずは、ひらがな、日常的によく使う漢字だけで十分。
慣れるまでは、お手本をよく見て書く。
どの位置に、どのくらいの長さで書くのか、どこに点を打つのか、どのように丸くするのか、、新しい言語の書き方を初めて学ぶような気持ちで、とにかくよく見て書く練習から始めます。
お手本をよく見ることで、自分の癖もわかります、癖がわかれば、治すべき箇所も見えてきます。これがわかると、汚文字脱却へのペースが一気に上がります。
筆ペンも必要であれば、こちらもオススメ。



私は、芳名帳用に筆ペンの練習もしたことがあります。
筆ペンの持ち方や使い方を確認し、名前・住所くらいは書けるように練習しておくと、安心です。
ただ、今は練習をやめてしまったので、必要に迫られた時には、間違いなく前日猛練習をすることになります。
それでも、オバさんになってから、一度練習したので、どうにかなるような気がしています。
本を買ってまでやりたくない、家にプリンターがある場合には、無料サイトの利用も便利です↓



練習用のマスが不要、お手本を見ながらコピー用紙や裏紙などに練習するのであれば、サイトの利用は便利です。
ひらがな・カタカナ・小学生で習う漢字のほか、名言・格言などの短文の例文が多数掲載されているので、飽きずに練習できます。
ペンはどうする?
自分と相性のよいペンをすでに持っているのであれば、そのペンで練習するのが一番でしょうが、私は家にあるボールペンやサインペンで練習していました。
必ずしも書きやすい、ペン先の滑りがいいとも限りませんが、不特定のペンで練習することで、自分の手や指とペンの相性があまり気にならなくなります。



相性というよりも、ペンの性能としてイマイチのこともあります。そのようなペンは、使うと疲れます。
潔く交換し、別なペンで練習する方が賢明です。
なお、日頃はお気に入りのペンで練習するとしても、たまには別な種類のペン、芯の太さが異なるペンなどでも練習することをおすすめします。



練習し始めた当初、私と相性のいいペンでばかり書いていました。
でも、そのペン以外で文字を書くと同じようには書けない、、という残念な経験をしてから、種類の違うボールペンや、サインペンなども使って練習するようにしています。
書き方に慣れるまでは、毎日短時間でも練習する
ひらがな・カタカナ・簡単な漢字など、文字の基本の書き方を、自分の目や手が覚えるまでは、毎日短時間でも練習するのが、早く上達するコツです。
個人差はありますが、1〜2週間もすればある程度整った文字が書けるようになります。1ヶ月も経つと、お手本を見なくても、お手本のイメージが浮かぶようになります。



美文字を書きたいのか、汚文字脱却なのかによっても、かかる時間も練習量も変わってきます。
また、文字によってはバランスがとりにくかったり、苦手意識を感じたり、油断すると癖が出てきたりします。1〜2ヶ月は毎日練習する方がいいです。
なお、「短時間」には、具体的な数値はないですね。
使える時間や自分の集中力に合わせて、調整するしかありません。
それでも、汚文字に戻ってしまったら、、
練習して、文字を書く習慣がつくと、自分の書く文字も落ち着いてきます。
ただ、また文字を書かなくなったりすると、文字を書くための筋力や運動機能は低下します。



私も、汚文字脱却後、再び1年ほど文字をほとんど書かない時期がありました。
提出書類などで、久々に字を書いたら、驚愕。
時は汚いし、腕も指も疲れるし、、、あきらかに劣化していました。
その時は、程度にもよりますが、お手本を見ながらまた練習。これに限ります。



今、再び、毎日少しずつでも文字を書くようにしています。
美文字ではありませんが、恥ずかしくない程度の文字に戻るには、2〜3日の練習ですみました。
ひらがなから復習すればいいのでしょうが、私は面倒なので、短文で練習。一度身につけておくって本当に大事です。
お手本をみて練習をするなら、先にご紹介した「ペン字の味方」が便利。
お手本なしでも、文字を書く習慣をつけたいなら、お気に入りの作家の文章を毎日少しずつ書いてみるのもオススメです。
私の今のお気に入りはこちら↓



1日1語。
数十文字の短文なので、続けれられる文字数です。
しかも、空海のさまざまな言葉を書写するので、学びも多く、精神的も落ち着くので、最高にオススメです。